「急速に進化したAIは、まるで人間が答えているかのように会話ができるようになった!」
「作曲をする。絵を描く。今までは人間にしかできないと言われていたクリエイティブなことまでも、AIはこなせるようになった!」
チャットGPTが一般的に使えるようになったのを機に、そんな話が頻繁に聞かれるようになりました。
本来AIは大量の単純作業を正確にこなすことが得意で、データの収集や分析、画像や音声の認識、言語処理など、さまざまな業界や分野で人間の能力を超えるような作業を行ってきました。
そしてその能力の効率化は急速にすすみ、その範囲はいずれ人間を超えるとさえ言われています。

シンギュラリティ(技術的特異点)という言葉があります。これは、AIが自らの学習能力を使って人間より賢い知能を生み出す事が可能になる時点を指す言葉です。
それは2045年に訪れるという見解やもっと早まるという話、そして逆に当分の間は起こらないというものまでありますが、いずれにしてもその地点に向かっているのは確かなようです。
そんなAIの急速な進化によって、人間の生活や仕事はどう変わっていくのでしょうか?
私たちの生活が便利になることは喜ぶべきことです。ただ一方で、AIが人間に代わって仕事をし、私たちの役割や価値を奪ってしまう可能性も十分に考えられます。
特に、AIの進化がこれからの雇用にどんな影響を与えるのかは、私たち還暦世代にとっても大きな問題です。
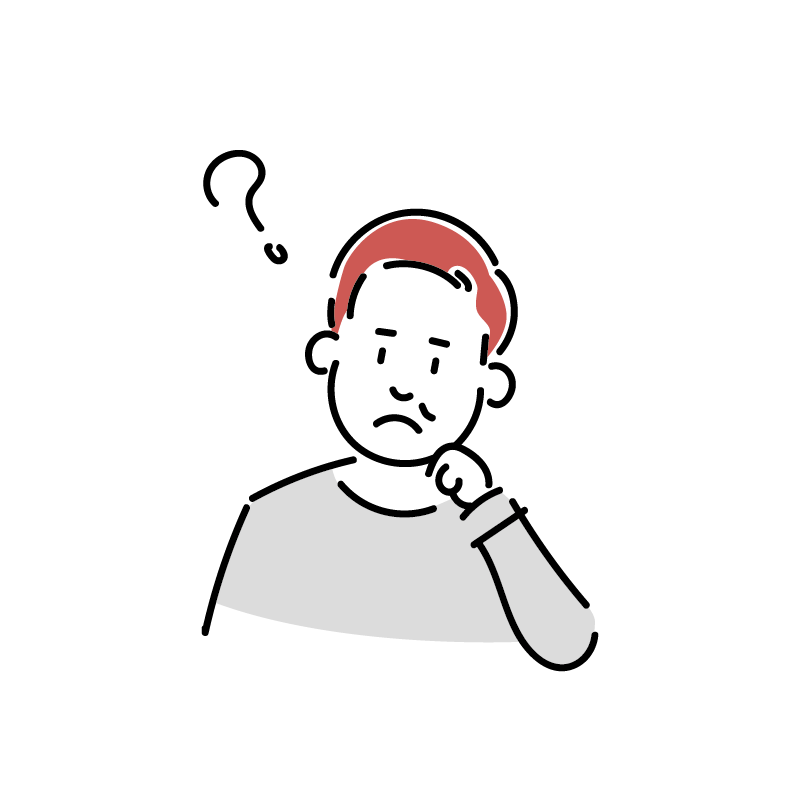
定年退職後にどんな働き方を選ぶべきか?スキルアップのためにどんな資格の取得を目指すべきか?ただでさえ条件の厳しい高齢者の雇用はどうなっていくのか?
この記事では、還暦世代にとって決して他人事ではない「AIの急速な進化によってこれからの社会に起こる雇用環境の変化」について、AIについての基礎的なことを確認しながらまとめていきます。
そのうえで、その変化に対応するために必要な3つのスキルについて解説したいと思います。
イノベーションの歴史とこれからのAI社会
イノベーションとは、新しい技術やアイデアを生み出して社会に広めること。代表的なのは、18世紀から19世紀にかけてヨーロッパやアメリカで起こった「産業革命」です。
この大規模な技術革新では、蒸気機関や鉄道、工場制度などが生まれ、社会に大きな変化をもたらしました。

農業社会から工業社会へと移行し都市化や人口増加が進み、その結果、雇用環境も変わりました。農業や手工業から工場労働への転換が起こり、労働者階級や労働運動が誕生したのです。
そして記憶に新しく、今現在も進行しているのが「情報革命」です。
《情報革命》
20世紀後半から21世紀にかけてコンピューターやインターネット、スマートフォンなどのイノベーションが生まれ、社会に大きな変化をもたらしました。
さらに、SNSの浸透などは新しい情報社会を形成し、人々の生活やコミュニケーションのスタイルを変えました。
GAFAMに代表される情報技術を核とした企業が世界規模で世の中に影響を与え、教育や娯楽などの方法が多様化し、雇用環境も変わり、サービス業や知識産業が拡大し、在宅勤務やフリーランスなどの柔軟な働き方が増えました。
このように、イノベーションは人類の歴史の中で、常に社会や文化、経済を変革してきました。そしてそれは今後も続いていくでしょう。私たちは、イノベーションに適応し、新しい価値を創造する能力を高める必要があるのです。

今まさに私たちは新たなイノベーションの波に直面しています。それがAI(人工知能)。
チャットGPTの出現で、AIという言葉を耳にしない日はないというくらい、私たちの生活に入り込んできています。もちろん、AIはそれ以前から様々な分野で活用されており、医療や教育、金融や法律などに革新をもたらしています。
そしてその進化と同時に、ある種の危機感が急速に広まってきています。
AIは人間の仕事や役割を奪い、雇用環境に深刻な影響を与える可能性がある!
AIには倫理や安全性、社会的影響などの面で課題もある!
このように、AIのはらんだ危険性を過度に恐れその存在自体を否定するような意見も多く聞かれますが、人間は不便な時代には戻れないのです。

洗濯機より洗濯板がいい、自動車より馬車がいい、スマホの無い時代のほうがいい・・。時としてそんなことを考えることもありますが、実際にはそんな世界を望んではいないのです。
イノベーションは、私たちの未来を切り開く力です。私たちは、AIを恐れるのではなく、AIを活用することで、より豊かで幸せな社会を創造することができるのではないでしょうか。
そのためにはまずAIについて、もっとよく知ることが必要です。
還暦世代が知るべきAIの基礎知識
AIとは、Artificial Intelligence(アーティフィシャル・インテリジェンス)の略。Artificialは「人工的な」、Intelligenceは「知能」という意味です。
つまりAIとは、人間の知能をコンピュータや機械に模倣させる技術のことです。
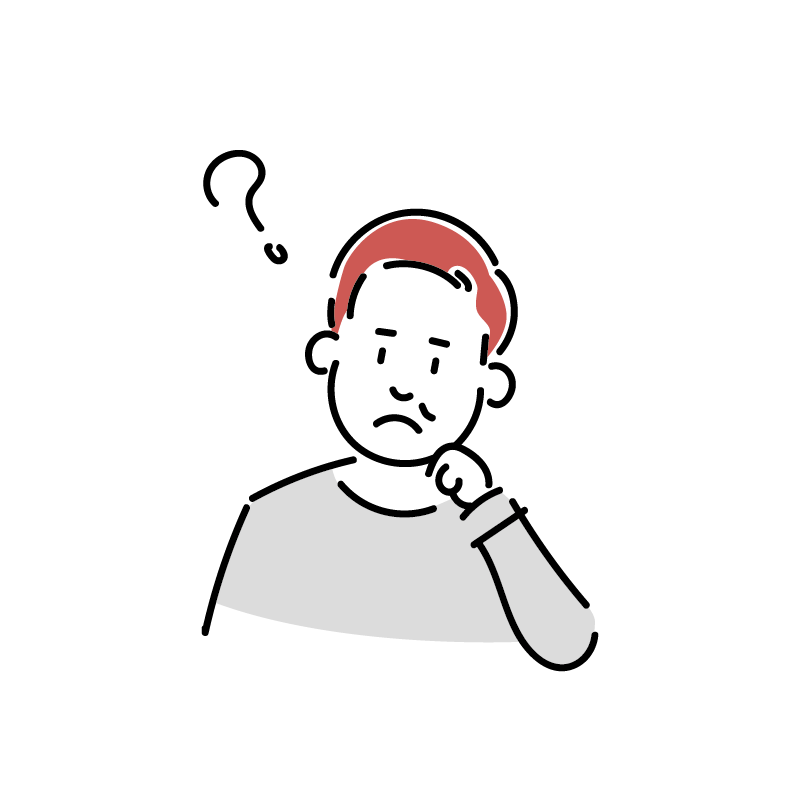
いったいどうやって模倣させるの?AIと人間の脳の違いって?・・というようなことを調べても、なんだか難しくてよくわからない。
ここで簡単に整理したいと思います。
《AIと人間の脳の違い》
AIと人間の脳機能は、どちらも物事を考えたり学んだりすることができますが、そのやり方や目的はまったく違います。
AIは人間が作ったプログラムに従って、データやルールを使って答えを出します。人間の脳は自然に生まれたもので、感情や経験や直感を使って判断します。
たとえば、「りんごとバナナはどちらが甘いですか?」とAIに質問すると、りんごとバナナの糖分の量を調べて数値で答えます。人間に同じ質問をしたら、自分が食べたことがあるりんごやバナナの味を思い出して感覚で答えます。
AIはデータをもとに正確な答えを出すことが目的ですが、人間は自分の感覚や意見を表現することが目的なのです。
AIと人間の脳機能のもう一つの違いは、AIは特定の課題に特化している点です。これに対して人間は多様な課題に対応できます。
たとえば、AIはチェスや将棋などのゲームでは人間より強くなることができますが、同じAIが他のゲームで人間に勝つことはできません。AIは一つのことを深く理解することが得意ですが、人間は色々なことを広く知ることが得意なのです。
AIは人間が教えたことしかできませんが、人間は新しいことにも自ら挑戦できます。つまりAIは、膨大な情報を整理して答えを出すことは得意ですが、音楽や絵画などの芸術の分野では人間を超えることはできないと言われています。
最近では絵を描いたり、作曲をしたりするいわゆるクリエイティブなAIも話題になっていますが、それはあくまでも過去に情報として取り入れたものをアレンジしただけのものであって、人間が独自に創造したものとは根本的に違うものだとされています。
このようにAIと人間の脳機能は根本的に違うもので、それぞれに長所と短所があります。AIは人間にできないことをできるようになるかもしれませんが、人間にしかできないこともあります。
AIは感情を持つようになるのか?
AIは、人間のように考えたり行動したりすることができる技術ですが、人間との決定的な違いは感情を持っていないということです。

2年ほど前「AIに感情が芽生えている」と主張していたグーグルのソフトウェアエンジニアがついに解雇され、大きな話題になりました。グーグルは、「私たちはAIに感情があるという主張には全く根拠がないことがわかっている」と正式にコメントしています。
事の真相は分かりませんが、それほどまでにAIが人間に近づいているという事実を認めないわけにはいきません。
 感情とは、喜びや悲しみ、怒りや恐れなど、心の状態や気分を表すもので、私たちの思考や判断、行動や対人関係に大きな影響を与えます。はたして、いつの日かAIは人間と同じように感情を持つことができるのでしょうか?
感情とは、喜びや悲しみ、怒りや恐れなど、心の状態や気分を表すもので、私たちの思考や判断、行動や対人関係に大きな影響を与えます。はたして、いつの日かAIは人間と同じように感情を持つことができるのでしょうか?
グーグルのコメントにあるように、少なくとも現段階では否定的な意見が主流なようです。

AIが感情のようなものを持つことができるとしても、それは人間の感情と同じものではなく、人間が作ったプログラムやデータに基づいて生成されるものだということです。
それは人間の感情と同じように複雑で多様で不安定なものではなく、また倫理や道徳や価値観に基づいて表現されるものではないでしょう。それはある意味では人間に対して友好的であるという保証のないものといえます。
AIの規制をめぐるここ最近の議論もこの点に関する疑念がもとになっているのでしょう。
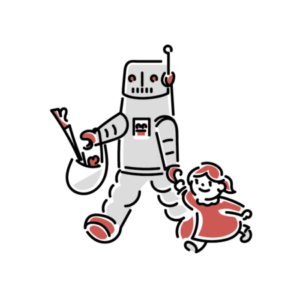 そもそもこのようなものを感情と呼ぶべきかどうかも分かりませんが、仮に感情と呼ぶとして、それが私たちの未来をどう変えるのかは、私たちの目的によって変わるのでしょう。
そもそもこのようなものを感情と呼ぶべきかどうかも分かりませんが、仮に感情と呼ぶとして、それが私たちの未来をどう変えるのかは、私たちの目的によって変わるのでしょう。
AIが人間の創造物である以上、AIが感情を持つことが私たちにとって良いことなのか悪いことなのかは、私たち次第ということになります。
AIに奪われる仕事と奪われない仕事
AIの進化の話題とともに常に大きく取り上げられるのが、「AIに仕事を奪われるのではないか?」という深刻なテーマです。

イノベーションの歴史を振り返ると、技術の進歩は常に雇用に大きな影響を与えてきました。産業革命の際の工業化に対する反抗で起きた「機械破壊運動」など、職を失うことに対する抵抗が常にありました。
しかし、結果的には技術の進歩をとめることなど出かなかったのです。
身近なことで言えば、自動改札機の導入で駅員の業務は大きく変わり、さらに自動運行システムにより運転士さえ要らなくなりつつあります。
スマートメーターの普及で電気やガスの検針員も不要になり、銀行の窓口業務の形も大きく変わろうとしています。
それでは、第4次産業革命といわれる技術革新の主役ともいえるAIの進化によって、私たちの雇用環境はどんなふうに変わるのか?
それを予測するために、まずはAIの特徴を確認して「AIが得意なことと苦手なこと」をはっきりさせてみましょう。
《AIの特徴》
- AIは人間の脳の構造や機能を模倣したものではなく、数学的なアルゴリズムやデータを用いて、特定の課題を効率的に解決することを得意としています。
- AIは人間の感情や倫理観、創造性などを持っていないので、善悪の判断をしたり、自ら目的や意思を持って行動することはできません。
- AIは人間が設定したルールや目標にしたがって意思決定や行動をするので、人間のニーズや意図を正確に理解したり、人間とコミュニケーションしたりすることはできません。
このようなAIの特徴を踏まえると、AI時代で仕事はどうかわるか?という問いに対する答えは、おのずと見えてきます。

単純で定型的な仕事はAIに代替される可能性が高いが、複雑で創造的な仕事は人間にしかできない。ということになるのではないでしょうか。
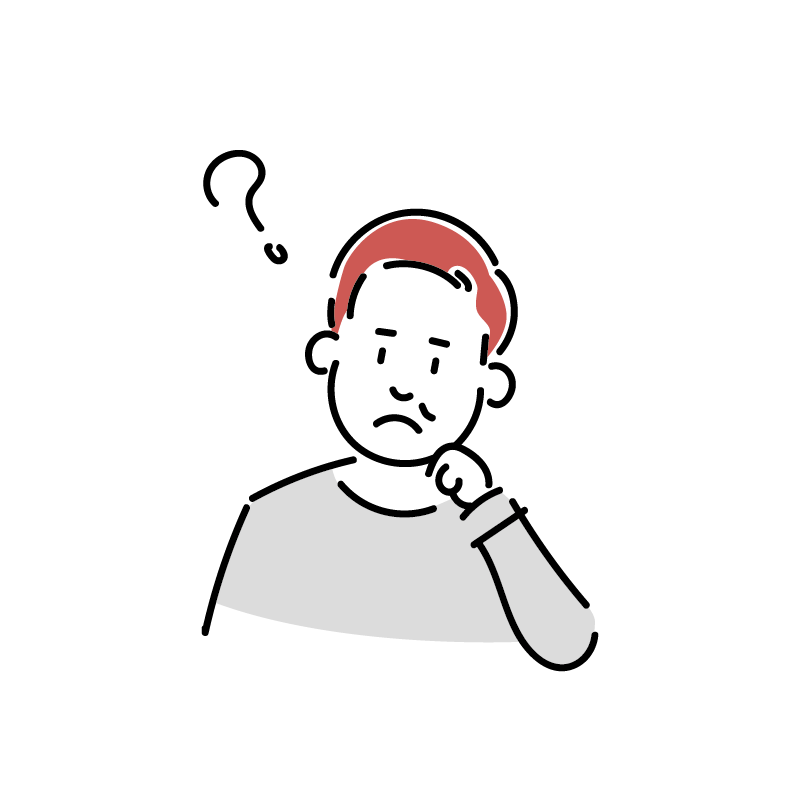
複雑で創造的な仕事って、具体的にはどんな仕事なんだろう?
オフィスでの仕事では、データ入力や計算などの単純作業はもちろんAIに任せることができますし、データを集めて情報を整理するような仕事もAIのほうが早く正確にこなせます。
しかし、企画や設計などの創造的なものや、提示された情報をもとに戦略を練ったり、人を管理してプロジェクトを動かすなどの仕事には、人間の発想力や感性が必要です。
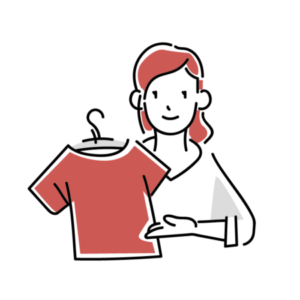 接客や販売などの分野でも、誰でもできる型にはまったサービスの提供はAIに取って代わられる可能性がありますが、顧客との信頼関係や感動体験を作るような独自性の強いものには、人間のコミュニケーション力や感情の部分が必要です。
接客や販売などの分野でも、誰でもできる型にはまったサービスの提供はAIに取って代わられる可能性がありますが、顧客との信頼関係や感動体験を作るような独自性の強いものには、人間のコミュニケーション力や感情の部分が必要です。
市場調査や集客はAIの力を借りることで効率的で確実なものにすることができますが、最終的にモノを売ったり契約を結ぶ段階では営業力や人間性が決め手となる場合が多くなります。

AI時代では、業界や職種に限らず、人間としての価値や能力を高めることが、仕事の成功や充実につながります。
AIは、私たちの仕事や生活を変えていくものですが、私たちの仕事や生活を決めるのは、私たち自身です。AI時代においても、私たちは自分の選択や行動に責任を持ち、自分の夢や目標に向かって努力することができます。
AI時代を恐れるのではなく、AIを活用して時代のながれにのることが必須となります。
還暦世代が身に着けるべき3つの必須スキル
AIによって効率化されていく仕事環境の中で自分の存在を重要なものにしていくにはどうしたらいいのでしょうか?
データの収集や分析、判断や推論、学習や改善などについては人間よりも高速で正確に処理できるAIにも、まだできないことや人間にはかなわないこともあります。
それは、人間の感情や価値観、創造性や想像力などに関わるものです。
仕事上でも重要な役割を果たすこれらの要素を満たすために必要なのが、次の3つのスキルです。
①ホスピタリティ ②マネジメント力 ③クリエイティビティ
《ホスピタリティ》
ホスピタリティとは、相手の立場に立って気遣いや配慮を示す態度や行動です。ホスピタリティは、サービス業や医療などの対人関係が重要な仕事では欠かせません。
飲食店や宿泊施設などで感じる「自分の気持ちを分かってくれている」という心地よさや、病気の時に「不安や心細さに寄り添ってくれている」という安心感は人間ならではのものです。
AIは、顧客のニーズや嗜好を分析したり、最適なサービスを提供したりすることはできますが、人間の感情や心理を読み取ったり、共感したりすることは不得意だからです。
プログラムされた通りに動くAIは柔軟性や臨機応変さに欠けます。そのため、AIが進化しても、人間のホスピタリティは必要不可欠なのです。
《マネジメント力》
マネジメント力とは、自分自身や他者を管理・指導・育成する能力で、組織やチームで働く場合に必要なスキルです。
部下や同僚が仕事に行き詰ったときやモチベーションが上がらない場合などに、その人に合わせた的確な提案や、心を動かす声掛けができるのは人間だけです。
AIは、目標や計画を設定したり、業務の進捗や成果を評価したりすることはできますが、他人の動機付けやコミュニケーションを行うためには、人間のマネジメント力は重要です。
《クリエイティビティ》
クリエイティビティとは、新しいアイデアや解決策を生み出す能力です。クリエイティビティは、イノベーションや発明などの創造的な仕事に必要な能力です。
AIが絵やイラストを描いたり、作詞作曲までできるようになったという話を聞くことがありますが、それは既存のデータや知識を並べ替えたり組み合わせたりしたものに過ぎず、人間の創造性や想像力には及びません。
AIが進化しても、感性や感覚などの主観的な要素を持つ人間のクリエイティビティには価値があります。
AIが人間の知能を模倣する技術である限り、私たちに残される仕事上の役割がすべて失われることはありません。

感情や価値観、創造性や想像力などに関わる人間らしさを活かしたスキルを身に着けることが、これからの社会では必須となるでしょう。
まとめ
AIの急速な進化によってこれからの社会に起こる雇用環境の変化について考えてみました。
「機械に仕事を奪われる」という恐れに近い不安は、テクノロジーの進化につきものだと言えますが、このAIについては今までとどこかしら違う感覚を持つのはなぜでしょうか?

AIは人間の価値観や判断基準に従って行動するとは限らず、自己学習や自己改善によって、やがて人間のコントロールを超える得体のしれないものだという印象を私たちに与えているからかもしれません。
しかし、AIについて基本的なことを確認することで、その不安は多少なりとも和らいだ気がします。
AIは私たちの仕事や生活を変えていくものですが、AIが人間の作ったプログラムに従い、データやルールを使って答えを出すものである以上、私たちの仕事や生活を決めるのは、私たち自身ということになります。
「ホスピタリティ」「マネジメント力」「クリエイティビティ」という3つのスキルは、感情や価値観、創造性や想像力などに関わる人間らしさを活かしたスキルです。
AIという私たちにとって重要な技術を活かし、上手に付き合うためには、私たちは知能や能力を高めるだけでなく、人間性や感性の面でも更に成熟しなければなりません。

AIに仕事を奪われない唯一の方法は、ここまで進化したAIにもまだできないことや、人間にはかなわないことが何なのかを知って、それを身に着けることではないでしょうか。
<<関連記事➡『AIが進化しても奪われない仕事とは?キーワードは「ホスピタリティ」』
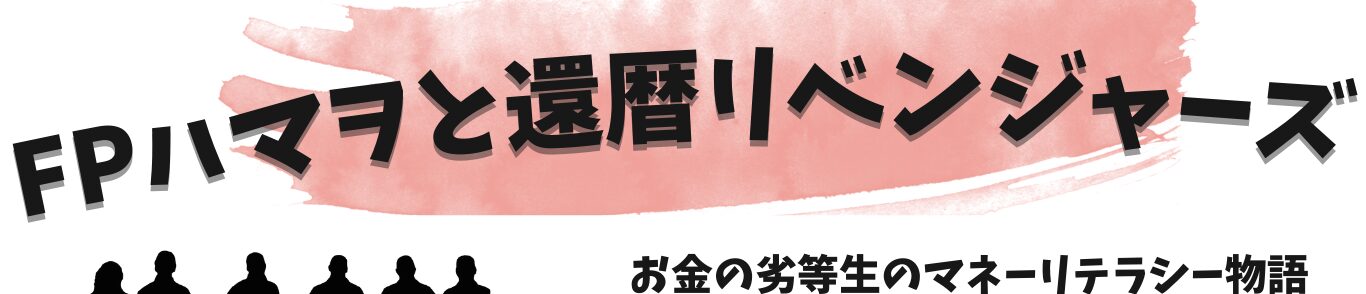



コメント