60歳の定年で会社を辞めてその後は悠々自適に・・という人は今や例外的になりました。
急激に減っている退職金、徐々にではあるものの確実に減っていく年金。それに若い世代の収入の低さも加わって、定年の年齢を過ぎてもまだまだ働き続ける必要がある人が大半です。

令和5年時点の60歳から64歳の就業率は男性が80%以上、女性が60%以上となっています。
「高年齢者雇用安定法」の規定で、いま働いている会社で60歳以降も働き続けることは難しくはありませんが、ほとんどの場合は給与が減少してしまいます。
とはいえ、60歳になって別の会社に就職するとなると、それもかなり高いハードルに思える。
人生の岐路ともいえるこの選択はとても悩ましいものですが、それ以上に深刻なのは、どちらを選んだ場合にも直面する可能性の高い「収入の減少」ではないでしょうか。
この記事では、60歳以降の働き方の現状と給与などの実態。
そして、給与が下がってしまった場合に受けられる救済措置についてまとめました。
給与の減少をカバーする2つの給付金
再雇用で働くと、ほとんどの場合は以前より給与が下がります。
どれくらい下がるかは会社によってかなり幅がありますが、半額近くになってしまうこともあるようです。
また、他の会社に転職した場合にも給与の大幅な減少の可能性はあります。
再雇用を選ぶとしても、再就職に挑戦するとしても、定年後の労働条件は決して甘くはないのです。

そうなった場合の救済措置として、雇用保険から「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」という制度が用意されています。
定年退職後の給与の減少をカバーする、よく似た名称でややこしいこの2つの給付金について、共通点と違う点に注意しながらみていきましょう。
2つの給付金の共通点
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」はとてもよく似ています。まずは共通点を分かりやすくまとめてみましょう。
《給付資格》
- 年齢が60歳以上65歳未満である。
- 今の給与が60歳時点の給与の75%以下に下がった。
- 今の会社で雇用保険に加入している。
- 雇用保険に5年以上の加入実績がある。
- 今の給与が36万3,359円未満である。
《給付金額》
厚生労働省発行の給付金額早見表による給付率は、
給与の低下率74.50%の場合の0.44%から
給与の低下率61.00%の場合の15.00%まで
0.50%刻みで設定されています。この給付率をいまの会社の給与にかけた金額が給付金額となります。
2つの給付金の違い
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」。名称も内容もよく似ているこの2つの給付金の違う点を確認しておきましょう。
《高年齢雇用継続基本給付金》
再雇用あるいは他の会社に転職した際に、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給していないことを条件に、60歳になった時点とそれ以降の収入を比べて、75%未満に下がった場合に、60歳になった月から65歳になった月まで支給されます。

「雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給していない」というのがポイント。
たとえば・・
●定年退職して同じ会社に再雇用された場合
通常は途切れなく働く形になり、失業手当を受給することはないので、受給対象になる場合があります。
●定年退職して違う会社に再就職した場合
途切れなく新しい会社で働き始めたり、働かない期間があっても失業手当を受給しなければ、受給対象になる場合があります。
受給期間は60歳になった月から65歳になった月まで。
《高年齢再就職給付金》
定年退職をして、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給している60歳以上65歳未満の人が、再就職して賃金が退職前の75%未満に下がった場合に、雇用保険の基本手当(失業手当)の支給残日数によって定められた期間(ただし65歳になるまで)支給されます。

「雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)を受給している」というのがポイント。
たとえば・・
●退職して失業手当を受給しながら再就職先を探し、就職した場合は受給対象になる可能性があります。
受給期間は雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の支給残日数によって決まります。
支給残日数100日以上200日未満:1年間(ただし65歳になるまで)
支給残日数200日以上:2年間(ただし65歳になるまで)
2つの給付金の注意点
「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」は雇用保険から支給されるため、雇用保険の他の給付金との関係で注意が必要です。また、給付額の計算も複雑なのでその点も確認しておきましょう。
- 申請日時点で雇用保険に加入して働いていて、その後も継続して雇用される見込みがあることが必要なので、いわゆる短期アルバイトなどの不安定な仕事の場合は受給できません。
- 雇用保険から支給される再就職手当を受給している場合は受給できません。
- 給与の低下率の点で、60歳の時点で受給資格に当てはまらなくても、65歳までのあいだに75%未満に低下することがあれば、その時点から受給資格が発生します。 逆に、受給中に75%を超えた場合はその月の給付金は支給されません。
- 支給額を計算する際の「60歳までの賃金月額」とは、60歳に到達する直前の6か月間の平均の給与です。(交通費、歩合給、残業代、皆勤手当などを含み、賞与は含まない)
- 高年齢雇用継続給付金は、2025年度から段階的に縮小・廃止されていく方針です。
まとめ
高年齢雇用継続給付金について、厚生労働省のリーフレットには
高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的としています。
となっているように、これらの給付金の目的は、高齢なった人に少しでも長く働いてもらうことです。少子高齢化で社会保障の維持が困難になりつつある中、支える側と支えられる側のバランスの維持が必須になってきます

60歳を境に収入が大幅に減ると高齢者の労働意欲が低下して、結果的に支えられる側の比率が増してしまいます。それを食い止める手段ともいえます。
「高年齢再就職給付金」が基本手当の支給残日数によって分けられているのもまた同じ事情です。少しでも早く再就職をして基本手当の受給者を減らしたいという理由で、多くの残日数を残した場合に得をするようになっているわけですね。
もちろん働く側の私たちにとっても、どんな働き方を選んだとしても減ってしまう可能性が高い60歳からの給与をカバーしてくれる給付金はありがたいものです。受給要件に該当する場合はぜひ利用しましょう。

ただし、この給付金は基本的に事業主、つまり会社側が申請するものです。会社の担当者が制度を熟知していない場合もあるので、こちらから積極的に行動することも必要です。
人生100年といわれる長寿の時代になり、年金をはじめとする社会保障制度は大きく変わりつつあります。法律や制度の改正に伴う移行措置や特例によって、ただでさえ複雑な制度がさらに分かりづらくなっています。

ほとんどの会社は60歳が定年。でも年金の受給開始の65歳までは働きたい。だから
会社には65歳まで雇用の義務がある。でも給与は大幅に下げてもいい。それでは困るから、下がった給与の補填のための給付金がある・・、なんだかへんな感じが・・。
冷静に見るとちょっと変なこの状況も、世の中が大きく変わる中では仕方のないことなのかもしれません。

残念ながら私たちには、社会の制度を直接変えることはできません。変えることができるのは自分自身だけなのです。
60歳はまだ人生の中間地点。どんな社会でも生き残れる人間になるために変化を受け入れ柔軟に対応していくことも必要なのでしょう。
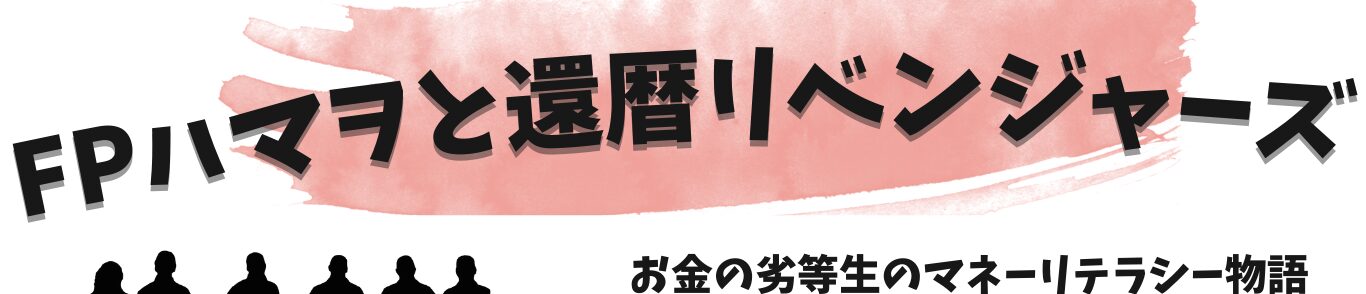



コメント