できればそんなことが起こらなければいい・・
地震や水害、そして世界が壊滅してしまうようなもっと恐ろしいことまで、私たちは儚い希望だけを頼りに日々を過ごしてはいないだろうか?
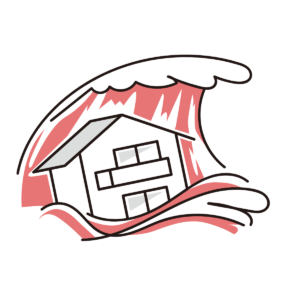 もちろん、そんな脅威の数々に対して私たちができることは限られています。
もちろん、そんな脅威の数々に対して私たちができることは限られています。
可能な範囲の備えをしたら、あとは祈るしかないというのもまた真実なのかもしれません。
結果的に、そんな災難は自分の身には降りかからなかった・・という可能性のほうが高いのです。
さて、ではかなりの確率で自分の身に起こることについてはどうでしょうか?
 人はみな年老いていく。
人はみな年老いていく。
➡高齢になれば身体の機能は衰えていく。
➡弱くなった身体では今までできていたことができなくなる。
➡生きていくためには誰かの手助けが必要になる。
これはかなりの高確率で、いや、生きている限りほぼ100%いずれは誰の身にも起こることなのです。

ということで、今回のテーマは「介護」です。そんなことは自分にだけは起こらない・・というのは決して賢い考えではありません。
介護が必要な人はどれくらい?
個人差はあるにせよ、還暦世代のみなさんのご両親は80代~90代がほとんどでしょう。
もちろん、現在も現役でバリバリ働いている!仕事はリタイヤしたが、趣味や社会貢献などの分野でハツラツと過ごしている!という方もいると思います。
しかし多くの場合、
自分の力だけで日常の生活を送るのはかなり無理がある。
認知の面でも衰えがあって、心配な場面も見受けられる。
というのが実情ではないでしょうか。
《要介護・要支援状態の方の人口比》
80歳~84歳では約11.3~26.2%
85歳以上では約59.7~60.1%
90歳以上では約72.7%(厚生労働省集計・令和5年度)
しかもこの数字は行政による認定を受けている方に限られます。つまり、介護サービスを受けずに家族が自力で面倒を見ているケースは含まれていません。

うちの親だけはそんなことにならない・・と思っている人には厳しい現実といえるでしょう。
現実的なことには現実的な対処をすることが大切です。まずその一歩として、最低限の知識をつけることが必要になります。
介護ってどれくらいお金がかかるもの?
介護が必要になった場合、その経済的負担はどれくらいなのでしょう?

親を想う気持ちはもちろんですが、経済的に余裕のない還暦世代にとっては、この「介護にかかるお金の問題」が大きな関心事であることは間違いありません。
その費用について知ったうえで、どのように備えるべきかを考える必要があります。
年間にかかる介護費用の平均は以下のとおりです。
《介護費用の平均年額》
【在宅介護】 平均約57.6万円(月額4.8万円)
※在宅介護とは・・
老人ホームなどの施設に入居せずに、自宅で介護を受ける方法。主要な介護は家族が行い、必要に応じて訪問介護やデイサービスなどのサービスを利用する。《メリット》住み慣れた環境で生活できるので本人の精神的な負担が少ない。
《デメリット》家族の負担が大きくなる。【施設介護】 平均約146.4万円(月額12.2万円)
※施設介護とは・・
老人ホームや介護老人保健施設などの介護施設に入居し、専門スタッフによる介護や生活の補助を受ける方法。《メリット》24時間体制で介護、医療のケアが受けられ、家族の負担が軽減される。
《デメリット》住み慣れた環境を離れることで本人の精神的な負担が考えられる。
在宅介護と施設介護をあわせた平均は、年間約93.6万円(月額7.8万円)となっています。

この費用をどのように賄うかということになるわけですが、まず最初に思い浮かぶのが公的介護保険です。
公的介護保険の基礎知識
40歳以上になると、会社員の場合は給与から介護保険料が天引きされます。自営業者などは納めている国民健康保険料に介護保険料が含まれるようになります。
毎月保険料を払っているにもかかわらず、介護保険について理解している人は少ないのではないでしょうか?
まずは、介護保険について基本的なことをまとめました。
公的介護保険の概要
公的介護保険は、40歳以上のすべての人が必ず加入する社会保険制度で、みんなで保険料を納めて、介護が必要になった人が所定のサービスを受けられる仕組みです。
被保険者は年齢によって2つに区分される。
【第1号被保険者】65歳以上
《保険料》原則として市町村が徴収する。(年金の受給額によって年金からの天引きの他、いくつかの方法がある。
《介護認定》原因を問わず、要介護・要支援状態になった場合。【第2号被保険者】40~64歳
《保険料》現在加入している医療保険の保険料と合わせて徴収される。
《介護認定》加齢に伴う「特定疾病」により要介護・要支援状態になった場合。
65歳以上は年齢のみで認定対象となりますが、64歳までは原因となる特定疾病が必要です。

介護状態になった原因によっては介護サービスが受けられないということですね。
自己負担割合と支給限度額
介護保険の考え方は健康保険と同じように、かかった費用のうち自己負担分を自分で支払い、その他の分が保険から支払われるというものです。
《自己負担割合》
介護サービス利用時の自己負担割合は、主に利用者の所得によって1割・2割・3割のいずれかに決まります。
とはいえ、ほとんどの高齢者は1割負担と考えていいでしょう。
さらに、住民税非課税世帯や生活保護を受けているなど、極端に所得が低い場合は食費・居住費等の軽減措置があります。

とはいえ、どんなに費用がかかってもそのほとんどが保険から支払われるというわけではなく、限度額の範囲内までとなります。
要介護度に応じて月ごとの支給限度額が定められていて、それを超えた分は全額自己負担となります。
《要介護度別の支給限度額(月額)》
要支援1 ・・・50,320円
要支援2 ・・・105,310円
要介護1 ・・・167,650円
要介護2 ・・・197,050円
要介護3 ・・・270,480円
要介護4 ・・・309,380円
要介護5 ・・・362,170円※地域によって単価が上がる場合がある。
※住宅改修費(手すり設置など)は20万円までは別枠で設定され支給限度額に含まれない。
※特定福祉用具購入費・居宅療養管理指導は支給限度額に含まれない。
支給限度額を超えてしまうと急激に費用が高額になってしまうので、

ケアマネージャーは可能な限り支給限度額を超過しないよう、要介護度別の支給限度額内に収まるようにサービス内容を調整をします。
※「ケアマネージャーの役割」については後の章で解説します。
要介護認定までの流れ
介護にかかる費用は介護認定の結果に大きく影響されることがわかりました。
次に、その介護認定に至るまでのステップをまとめてみましょう。
ステップ1. 申請手続き
【申請場所】
本人の居住地の市区町村窓口
※地域包括支援センターや居宅介護支援事業者が代行することもできる。【必要書類】
要介護認定申請書
介護保険被保険者証または健康保険証
主治医の情報(病院名・医師名など)
ステップ2. 訪問調査(一次判定)
【調査内容】
心身の状態(移動・食事・排泄など)の聞き取り
認知機能や日常生活動作の評価
※市区町村職員または委託ケアマネジャーが行う。
ステップ3. 主治医意見書の作成
【提出方法】
申請時にある主治医情報をもとに市区町村が直接医療機関に依頼する。
【記載内容】
疾病状況・認知症の程度・特別な医療行為の必要性
ステップ4. 判定
【一次判定】
調査データをコンピュータで分析し暫定区分を算定する。
【二次判定】
介護認定審査会が一次判定結果と主治医意見書を審査する。
ステップ5. 結果通知
【期間】
原則、申請日から30日以内
【通知内容】
要支援(1もしくは2)・要介護(1~5)・非該当(自立)のいずれか。
※介護保険被保険者証(区分を記載したもの)が同封される。
ステップ6. ケアプラン作成
【要支援1・2】
地域包括支援センターが介護予防計画を作成する。
【要介護1~5】
居宅介護支援事業者のケアマネジャーが個別ケアプランを作成する。
以上のような流れで介護認定が行われ、介護予防計画やケアプランに沿って介護サービスを受けることができるようになります。
公的介護保険の登場人物と場面
公的介護保険について、お金の面と介護サービスを受けるまでの流れを見てきました。
なんとなく介護保険の仕組みがつかめてきたことと思います。

しかし、いざ実際に介護が必要ななった時に「誰が関わって、どこに相談して、どう進むのか?」をちゃんと理解できているでしょうか。
どことなくボヤっとした印象があるとしたら、それは登場人物の多さによるものかもしれません。
健康保険の場合の登場人物はいたってシンプルです。
①被保険者(医療を受ける人)
②保険者(健康保険組合や市区町村)
③医療機関(病院)
基本的にこの3者だけですが、介護保険にはもっと多くの人が関わります。
ということで、ここでは公的介護保険に関わる登場人物(職業や組織)とその役割。そしてその人物が登場するシーンをわかりやすく整理しておきましょう。
登場人物とその役割
①【介護を受ける人】(被保険者)
40歳以上は保険料を支払い、65歳以上で介護が必要になった時にサービスを利用できます。(※原因によっては65歳未満でも受けられる場合があります)
②【市区町村】(保険者)
介護保険制度の運営者。保険料の徴収や要介護認定の窓口になります。
③【主治医】(かかりつけ医)
要介護認定の際に「主治医意見書」を提出します。
④【認定審査会】(医師や介護の専門職)
市区町村に設置されており、要介護度の審査を行います。
⑤【ケアマネジャー】(介護支援専門員)
利用者とサービス事業者をつなぎ、ケアプランを作ってくれる、いわば介護の司令塔。
⑥【介護サービス事業者】
訪問介護やデイサービス、施設などを提供する介護のプロ集団。市の指定を受けています。
⑦【地域包括支援センター】
自治体ごとに複数設置されている相談窓口。介護予防や要支援レベルの人のサポートもしてくれます。
登場人物が活躍する場面
登場人物が出揃ったところで、誰がどんな場面で登場して活躍するかを、時系列でざっと見ていきましょう。
①介護が必要になった場合に備えて【介護を受ける人】は40歳から保険料の支払いを続ける。※基本的に65歳になると介護保険のサービスが受けられるようになる。
②要介護の兆しが見えたら、【介護を受ける人】(本人や家族など)が 【市区町村】に「要介護認定」の申請を出す。
※申請書の主治医の欄に日ごろ受診している医療機関と医師名を記入する。
③【主治医】は市区町村からの依頼を受け、「主治医意見書」を提出する。
④【市区町村】の職員などが訪問調査を行い、【認定審査会】が調査結果や医師の意見をもとに「要介護度」を決定する。
⑤介護認定が出た後、選ばれた【ケアマネジャー】がケアプランを立てる。
※ケアマネは自分で探すこともできるが、市町村や地域包括支援センターで紹介してもらったり、病院の医療ソーシャルワーカーが紹介してくれることも多い。
⑥ケアプランに沿って【介護サービス事業者】による介護サービスがスタートする。

ケアマネを選ぶタイミングは要介護認定の結果が出たあとが基本ですが、実際には介護申請前や申請中など、状況によってさまざまなケースがあります。
公的介護保険に関係する登場人物と、いつ、どんな場面で活躍するのかがイメージできたでしょうか?
登場人物が多くてややこしそうに感じるかもしれませんが、実際には、市区町村の介護保険課や地域包括支援センター相談窓口に相談すれば、介護保険の手続き、今後の流れ、必要な書類などすべて教えてくれます。
そのあとの流れは自然に生まれてくるので、心配する必要はありません。
まとめ
両親の世代はまさに介護を受ける中心にあり、自身も近い将来同じ立場になるかもしれません。
どちらにしても、還暦世代にとって介護の問題は決して他人事ではありません。
誰もが明日は当事者になる可能性があるのです。
にもかかわらず、ほとんどの人は必要な介護の知識を持っていないのが実情ではないでしょうか?
「どうか自分には関係ないことでありますように・・」
そんな風に願いながら心のどこかで不安を感じながら過ごすより、最低限の知識を身につけて、いざという時に慌てず動けるように、今のうちから関係者の顔ぶれや相談先をイメージしておいた方がいいでしょう。
介護には登場人物、つまり関わる人が多く、誰がどんな役割をするのかを理解するのは簡単ではありません。
とはいっても、しかるべき相談窓口で現在の状況を伝えることで、必要な手続きが自然と進んでいくような仕組みになっています。

いちばん避けなければならないのは、よくわからないからといって、誰にも相談せずに一人で心配事を抱え込むことです。
忘れてはいけません。誰にとっても介護は自分のことになるのです。
少しでも心配なことがあるなら、市町村の介護保険の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。
相談することには何のリスクも無いのですから。
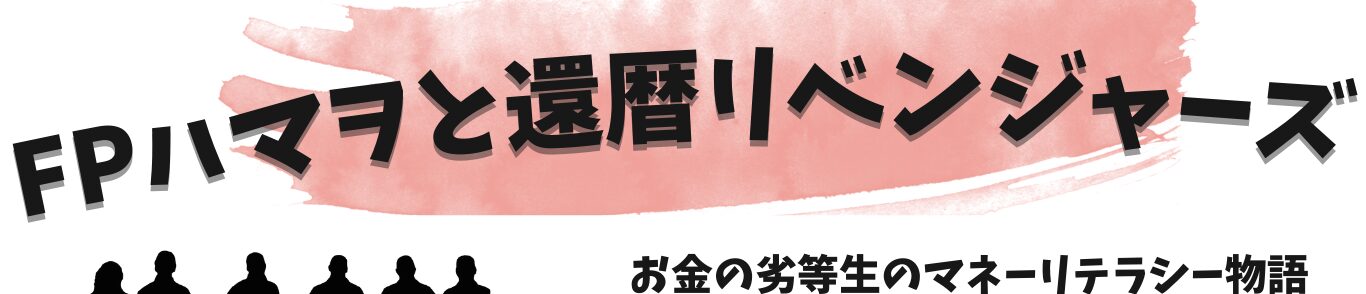



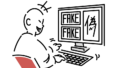
コメント