いま手元にある資金や収入の一部を使ってそれを増やすことができたら・・
それは還暦世代に限らず、おそらくほとんどの人が考えていることでしょう。
そのために証券口座を開設して株式や債券に投資をしたり、休日に競馬場に足を運んだり、年末になると宝くじのまとめ買いをしたりと、それぞれに回収を夢見て投資をしているのですから。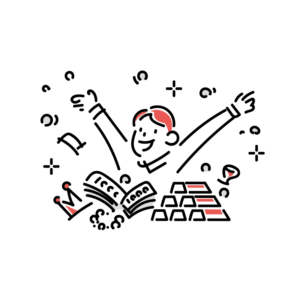
しかし当然のことながら、投資に確実なものは無い。どんなものにもお金が減ってしまうリスクがあるのです。
それどころか、場合によっては人生を大きく狂わせてしまうことだってあります。
でももし、

65歳から10年間生きていることさえできれば、確実に支払ったお金以上のものがもらえるとしたらどうでしょうか?
これは決して怪しい詐欺のような話ではありません。
国が運営している「国民年金」の話なのです。
 年金受給の年齢に近づいて、もらえる金額の少なさに老後の不安を感じている人も多いはずです。
年金受給の年齢に近づいて、もらえる金額の少なさに老後の不安を感じている人も多いはずです。
とくに国民年金加入者の場合、若い頃、生活に余裕がなく保険料をきちんと納めることができずに未納や免除の期間があれば、それはもらえる年金の額に大きく影響します。
こんなことなら保険料はしっかり納めておくべきだったと、過去を悔やんでいるだけでは未来は変わりません。
これからのことに意識を向けるべき時なのです。
年金増額の方法には、受給開始を遅らせる「繰り下げ受給」や、60歳以降も厚生年金に加入して働く「経過的加算」などがありますが、ここでは、

国民年金の未納などで満額受給ができない人のために用意されている「国民年金の任意加入制度」についてみてみましょう。
国民年金の基礎知識
国民年金は20歳から60歳のすべての人が加入しなければなりません。
勘違いしがちですが、会社員の人が払っている厚生年金の保険料には国民年金の分も含まれています。
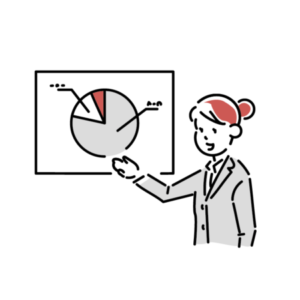 そしてこれも勘違いが多いですが、会社員に扶養されている専業主婦は国民年金の加入者です。ただし、保険料の納付は免除されている。
そしてこれも勘違いが多いですが、会社員に扶養されている専業主婦は国民年金の加入者です。ただし、保険料の納付は免除されている。
これが勘違いを生むややこしさなのです。
私たちが65歳からもらう老齢基礎年金の金額は、この国民年金の保険料として納めた金額に応じて決められます。
保険料は1カ月あたり月額17,510円(令和7年度・年齢や収入にかかわらず定額)
受給額は1年間で831,696円(令和7年度・20歳から60歳のすべての期間に納めた場合)

この満額の831,696円を基準として、納めていない期間分が減額されるということです。
そして「任意加入制度」の目的は、この減額されてしまった分を取り戻すことなのです。
国民年金の任意加入制度の目的
20歳から60歳までの40年間(480か月)に漏れなく保険料を納めていれば、65歳からもらえる老齢年金は満額になります。
とはいえ、すべての人がそうすることができるとは限りません。それは受給額の平均を見ればわかります。
令和6年度の受給月額は満額で68,000円ですが、平均値は56,000円(現時点では未発表のため推測値)となっているからです。

当然のことながら、受給年齢が近づいて老後の生活資金への不安がが現実的になってくると、「できることなら満額をもらいたい」と思う人も多くなります。
そういう人に向けて用意されているのが「任意加入制度」なのです。
任意というからにはもちろん強制ではありません。保険料を納めた分に応じた受給額で構わなければそのままでいいし、他の制度を利用した増額を検討するのであれば、それも自由なのです。
国民年金の任意加入の条件
国民年金の任意加入はその目的から考えて、すべての人ができるわけではありません。日本年金機構の説明では任意加入の条件を次の5つとしています。
《国民年金の任意加入の条件》
1、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3、20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4、厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5、日本国籍を有しない方で、在留資格が特定活動や特定活動ではない方
簡単に言えば、
「納付月数が満額需給に足りていない」場合、
「繰り上げ受給をしていない」人で、
「他の年金制度に加入していない」のであれば、
「60歳から65歳の期間」にかぎり、
「納付月数が480月(40年)になるまで」
加入できるということです。(国籍、住所地についての条件は省略)
任意加入で増える年金額
平均寿命が伸び人生100年といわれるようになったとはいえ、自分がいつまで生きられるのかは誰にもわかりません。
そうなると気になるのが、
任意加入で支払った保険料と増額される年金の額との関係です。
《60から65歳までの5年間、任意加入で保険料を納めた場合の増額金額》
5年に支払う保険料の額:17,510円(令和7年度の月額保険料)×60カ月(5年間)=1,050,600円
1年間に増える受給金額:831,696円(令和7年度の満額)×60カ月÷480カ月=103,962円
このように、1,050,600円の保険料を支払うと、1年間にもらえる年金が103,962円増える計算になり、支払った1,050,600円は、103,962円の年金を10年間もらえば、ほぼ取り戻せることになります。

この比率は月数にかかわらず一定なので、何か月間任意加入したとしても、損益分岐点は年金をもらい始めて約10年後というわけです。
つまり、それ以降にもらう分については得をするということなのです。
年金受給が始まる65歳から10年以上生きられるかどうかは誰にもわかりません。
しかし、生きられると信じるなら、これはかなり効率の良い投資ということになるのではないでしょうか。

また、この任意加入の保険料に月額400円の保険料を上乗せして支払う「付加年金」という制度もあり、これは年金を2年間受給すれば元が取れるというとても効率の良いものです。
この上乗せで、任意加入の損益分岐点をさらに早めることも可能なのです。
国民年金の任意加入の注意点
《国民年金の任意加入の注意点》
①加入できるのは60歳から65歳の5年間のみ。この期間ならいつからでも加入できますが、さかのぼって加入することはできません。この5年間すべての期間に加入したい場合は60歳から加入しなければならないので、60歳の誕生日までに手続きが必要になります。
②年金定期便の「合算対象期間」の欄に月数の表示がある場合は任意加入による増額の計算が異なります。
③年金受給資格のための120ヶ月(10年間)の保険料を納付していない場合、受給資格を得られる月数に達するまで、65歳から70歳の期間もこの任意加入制度が利用できます。(特例任意加入)

任意加入によって納めた保険料と増える受給額の計算には複雑な部分もあるので、免除期間の免除比率などによる違いには注意が必要です。
まとめ
国民年金の未納保険料は追納(後払い)もできますが、10年前までのものに限られているので、還暦世代になってから若い頃の分を納めたいと思っても、それはできません。そんな時、この「任意加入」は有効な制度なのです。

厚生年金に加入して働いていれば「国民年金の任意加入」はできませんし、収入によっては繰り下げ受給による増額の効果が得られない可能性もあります。
人生100年といわれる時代になり、60歳から65歳の就労率は割合は80%を越えているといいます。
その「定年後の働き方」と「年金の受給」はたいへんかかわりが深いものです。
不明な点は年金事務所などに確認して、自分にとっての最良の選択をしなければならないでしょう。
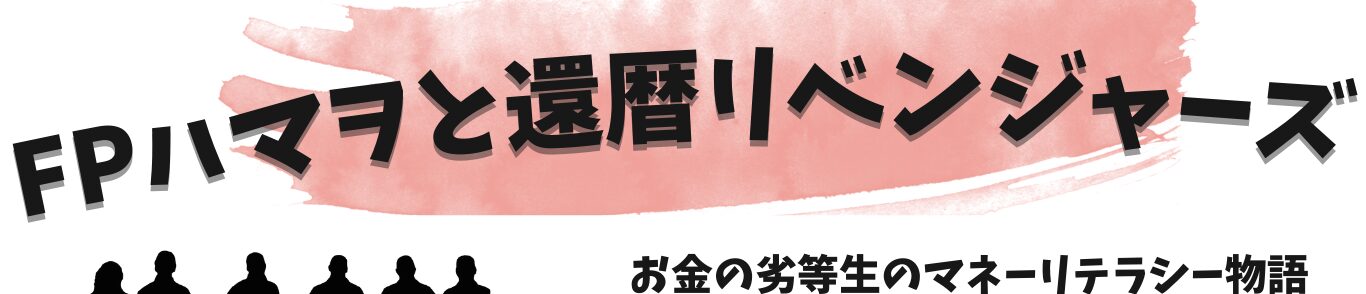
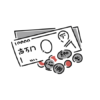


コメント