「NISAって、若い人がやるものでしょ?」
そう考えている還暦世代はけっこう多いのではないでしょうか。
そう思うのも仕方ありません。
本来、NISA制度を使っての投資は「長期」と「分散」と「積み立て」を前提に推奨されていますから、若いうちに始めたほうが有利だというのはひとつの真実です。

しかし、人生100年時代と言われる今、60歳は「老後のスタート」ではなく、むしろ「第二の人生の始まり」だと言えます。
平均寿命や健康寿命が延びて、60歳を過ぎても、あと20年、30年、もしかしたら40年と元気に暮らす時代、長期的な視点で資産を守りながら増やす選択肢として、NISAは十分に意味を持つ制度だといえます。
この記事では、60歳からNISAを始めることが手遅れではない理由について、長寿化の現実や制度の特性を確認しながら、わかりやすく解説します。
NISA制度の基礎知識
60歳からのNISAについて考えるにあたって、まずはNISA制度の基本を押さえておきましょう。
《NISA制度の基礎知識》
NISA(ニーサ)とは、「少額投資非課税制度」のことで、投資で得た利益に税金がかからないお得な制度です。
通常、株や投資信託で出た利益には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を使えば、一定の枠内でその税金がゼロになります。
2024年からは「新NISA」として制度が大きくリニューアルされたことで、投資枠が広がり、非課税期間も無期限となりました。
また、よく比較される制度「iDeCo(個人型確定拠出年金)」と違い、使い道に制限がなく、目的に応じて自由に引き出せるのもメリットです。
年齢制限もないため、もちろん60歳からでも始められる制度です。

注意しなければならないのは、NISAはあくまでも「投資」ですから、銀行預金などの「貯蓄」と違い、元本は保証されないという点です。
元本保証のない、ある意味で「リスク」のあるものを国として推奨しているのも、「長期・分散・積み立て」を前提にしたうえでの話です。
なぜ「長期・分散・積み立て」がNISAの基本なのか?
投資にはどうしても価格の変動リスクがあります。

リスクという言葉には「悪いこと」というイメージがありますが、「良いこと」も含めた「変動」全体を意味しているのです。
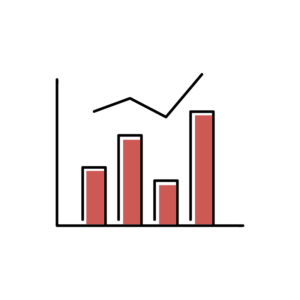 価格が上がったり下がったりする中で、安定して資産を増やすには、「長期・分散・積み立て」の3つがとても大切です。
価格が上がったり下がったりする中で、安定して資産を増やすには、「長期・分散・積み立て」の3つがとても大切です。
投資におけるそれぞれのの言葉がもつ意味を解説します。
《長期》できるだけ長い期間、投資を続けることで、相場の一時的な上下に振り回されず、平均的に安定した成果が期待できます。「今日と明日の価格」や「今年と来年の価格」を比べるのではなく、
「今日と20年後の価格」の違いを予測した場合、価格が下がる可能性がきわめて低いことは長い歴史の中で証明されているからです。
《分散》ひとつの銘柄や国に集中するのではなく、複数の商品や地域に投資することで、リスクを分け合うことができます。
たとえば、日本株だけでなく、アメリカ株や世界全体のファンドに分ける投資方法です。
《積み立て》一定額をコツコツと定期的に投資することです。
結果的に、価格が高いときは買う量は少なく、安いときには多く買うことになり、平均購入価格を下げられる効果があります。

この買い方は「ドルコスト平均法」といわれ、株価を気にする必要もなく、安全だといわれています。
この3つの基本を守ることで価格変動の影響を最小限にすることができます。
そのうえで、非課税というメリットを最大限に活かしながら、安定した資産形成を目指すことがNISA制度を利用する意味なのです。
60歳からNISAを始めるのは遅い?
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に税金がかからない、とてもお得な制度です。

ただ、そもそも「利益を得る」ための前提が「長期間の積み立て」ですから、「まだまだ時間のある若い世代向け」と思いがちです。
しかし冷静に考えてみると、現在の日本人の平均寿命は、男性で約81歳、女性で約87歳です。
 健康寿命も延びていて、60代で働くのは当たり前、70代や80代で元気に活動している人も珍しくありません。
健康寿命も延びていて、60代で働くのは当たり前、70代や80代で元気に活動している人も珍しくありません。
つまり、60歳にとっても「まだまだ先は長い」のです。
長寿化の最大の課題は、お金が長く必要になること。公的年金だけでは、ゆとりある老後生活は難しいと言われています。
特にお金に余裕のない還暦世代にとって、まだ長く続くこれからの生活を、今あるものだけで賄うことはできません。

これからも働いて収入を確保して、その収入の一部を効率よく増やしながら老後に備える必要があるのです。
その準備方法のひとつとして、NISAは有力な選択肢といえます。
60歳からのNISA活用のメリット
今のような超低金利時代に、銀行預金ではお金はほとんど増えません。
増えないどころか、インフレによって「お金の価値が目減りする」リスクすらあるのです。
そこで注目されるのが「投資」です。

しかしそれは、ギャンブルのような投機的なものではなく、着実に資産を形成していくものでなければいけません。
そういう意味で、月々少額のつみたてをコツコツと続けるNISAのような投資方法は有効です。
たとえば、年3〜5%程度のリターンを期待できる商品を10年間保有すれば、資産はそれなりに育ちます。しかも出た利益は非課税です。

60歳からNISAを始めることは、「大きく増やす」よりも、将来に備えて「お金を守る・活かす」という視点で考えるべきなのです。
「長期・分散・積み立て」の基本を守ることで、比較的安全に資産形成ができるNISA制度ですが、他にも注意すべき点があります。
60歳からのNISA活用の注意点
繰り返しになりますが、投資にリスクはつきものです。
長期的にはかなりの高確率で価格の上昇が見込めるNISA制度での運用ですが、短期的には価格が大きく下がることもあります。

絶対に避けなければならないのは、この、価格が下がっているタイミングで売却して現金に換えることです。そんなバカなことはしないよ・・と思うかもしれませんが、意外とそういうことが起こります。
よくあるのが。、株価が急激に下がり始めたときです。
「これ以上下がる前に、今のうちに売ってしまおう!」という気持ちからですが、これはNISA制度の基本である「長期投資」の意味を忘れています。
そしてこんなケースも、
「急にまとまったお金が必要になった!どうしよう!」そんな時に、資産がNISAで積み立てているお金しかない場合、損するのを承知で売却するしかないということになります。
その場合を考えると「貯蓄+運用」という考え方が必要になります。
想定外の出費などで急なお金が必要になった場合に備えるには銀行預金などの貯蓄が有効です。
銀行預金は利息がほとんどつかず、インフレによって価値が目減りするリスクのあものですが、元本保証というメリットがあります。

リスクを取りすぎないためにも、生活資金の半年〜1年分くらいは現金(銀行預金など)で確保しておく必要があるでしょう。
そのうえで投資にまわす金額を考える必要があります。
60歳からの投資には安心感も大切ですから、投資にまわす金額は、「当面は使わなくていいお金」の範囲にとどめて、精神的な負担を減らすべきでしょう。
まとめ
60歳からNISAを始めることに意味があるのか?
NISA制度の仕組みやメリットについて知っている人ほど、ぶつかるのがこの疑問です。
結論から言えば「おおいに意味があります」

「長期の積み立て」というキーワードに戸惑う気持ちはわかりますが、今の世の中を冷静に見れば、年齢についての思い込みを一度見直す必要があることに気がつきます。
人生100年時代、60代はまだ先の長い人生の途中です。
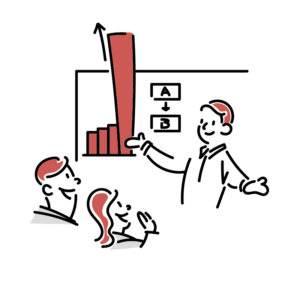 もちろん、NISA制度を利用した投資は期間が長ければ長いほどメリットが生かせるのは事実です。
もちろん、NISA制度を利用した投資は期間が長ければ長いほどメリットが生かせるのは事実です。
30年、40年という期間があれば資産は驚くほど増えていきますから、若いうちから始めるに越したことはありません。
とはいえ、10年~15年という期間でも積み立て投資のメリットはじゅうぶん見込めます。
還暦世代からの投資の目的は大きく儲けることではありません。

まだまだ先の長い人生に必要なお金のために、今できる準備をできるだけ効率よくしておくことなのです。
「貯蓄+運用」という基本を忘れずに、生活を守るお金は銀行預金などの貯蓄で準備したうえで投資にチャレンジするべきではないでしょうか。
NISA制度は、たとえ60歳を過ぎたとしても、この後の人生を豊かにするための心強い味方になるはずです。
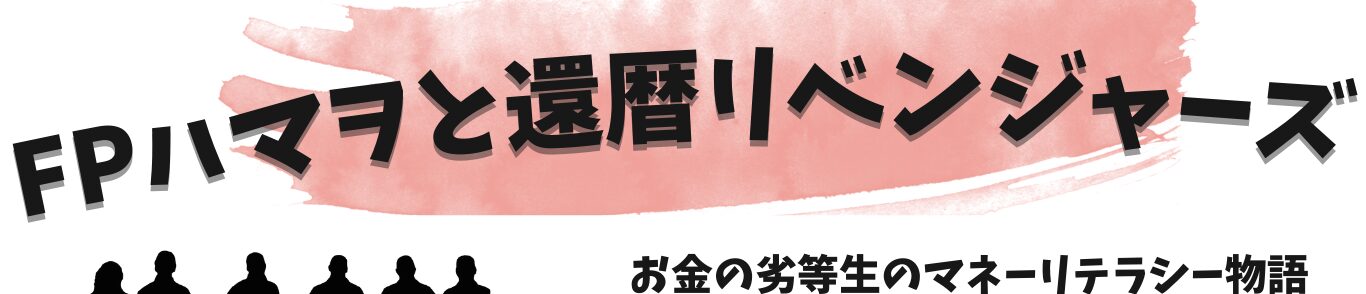
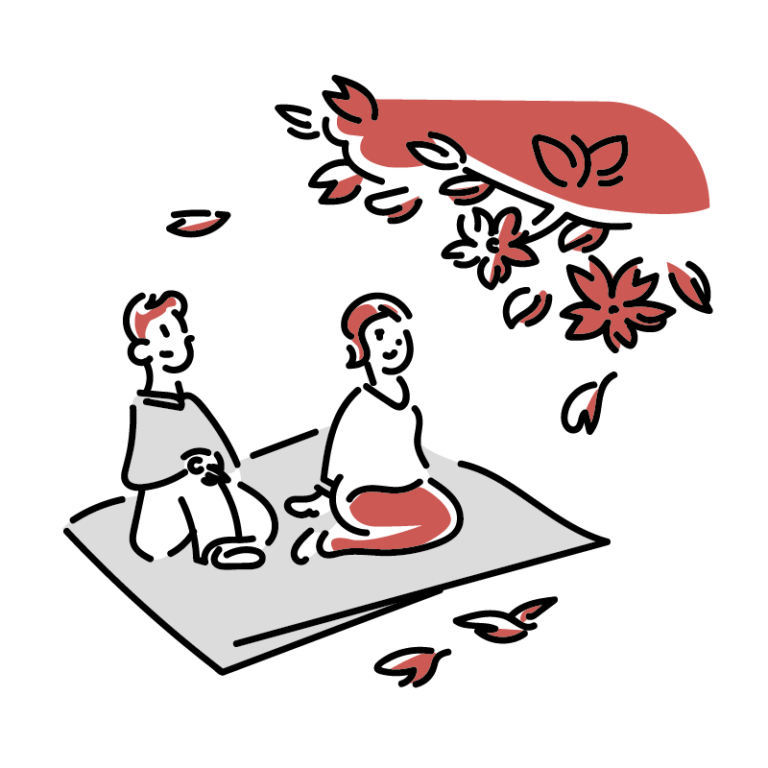
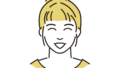

コメント