還暦世代は保険見直しの時期でもあります。
長年加入していた保険が満期を迎えたり、子供の独立などで必要な補償内容が大きく変わったり。
また、60代になると病気や入院のリスクを実感することも多
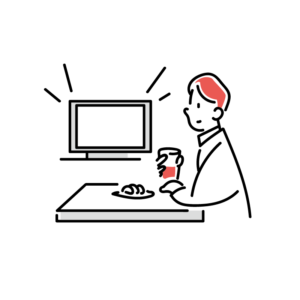
くなり、将来の医療費に不安を感じることもあるでしょう。
そこへ、「保険に入らないと危ない!」「医療費で家計が崩壊する!」といった広告がテレビから流れてくる。
つい不安になって新たに保険に加入したり、補償を増やしてしまう方が多いのも仕方がないのでしょう。

でもちょっと待ってください。日本には「高額療養費制度」という公的健康保険による強力なサポートがあることをご存知でしょうか?
この制度を知っていれば、「本当に必要な保険は何か?」という真実が見えてきます。
この記事では、高額療養費制度のしくみを60代の場合の事例を交えながら解説し、無理や無駄のない保険の見直し方法について考えます。
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、1か月間に支払う医療費が高額になった場合、その自己負担額に上限が設けられている制度です。
これは健康保険に含まれるもので、協会けんぽ・組合健保・国保のすべてに共通の制度です。
仮に長期の入院や大がかりな手術で1か月の医療費が100万円かかったとします。

保険証を提示すれば自己負担額は3割の30万円になるわけですが、その30万円の負担はかなり大きく、家計を圧迫してしまう・・というか、そもそも払えない場合も十分あり得ます。
そういう場合に、その自己負担の上限を超えた分が後日払い戻されるのがこの制度というわけです。
ただし、対象となるのは、病院やクリニックでの診療、薬局での処方薬の費用に限られ、差額ベッドや先進医療、入院中の食事代などは対象外になります。
60代の自己負担限度額はどれくらい?
気になるのはその自己負担限度額ですが、高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢と所得によって決まります。
60代はまだ70歳未満の「現役世代」として扱われるため、次のような所得区分に応じて自己負担の上限額が設定されています。
| 所得区分 | 自己負担限度額(1か月) | 備考 |
|---|---|---|
| 区分ア(年収約1,160万円超) | 約252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 高所得者層 |
| 区分イ(年収約770万~1,160万円) | 約167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 高収入会社員など |
| 区分ウ(年収約370万~770万円) | 約80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 多くの60代が該当 |
| 区分エ(年収370万円以下) | 約57,600円 | 退職後の年金生活者など |
| 区分オ(住民税非課税) | 約35,400円 | 低所得世帯 |
60代での実例シミュレーション
ここで、多くの60代が該当する《区分ウ》(年収約370万~770万円)と、退職後の年金生活者などに多い《区分エ》(年収370万円以下)についてシミュレーションをしてみましょう。
《区分ウ》会社勤めの60代男性(年収500万円)の例
- 1か月の医療費:800,000円(入院+手術)
- 自己負担3割:240,000円
- 80,100円+(800,000円−267,000円)×1% = 85,430円
- 実際の支払い:85,430円
《区分エ》退職後の年金生活者(年収280万円)の例
- 医療費:600,000円(通院+短期入院)
- 自己負担3割:180,000円
- 上限額:57,600円
- 実際の支払い:57,600円
高額療養費の立て替えが難しいときの対処法
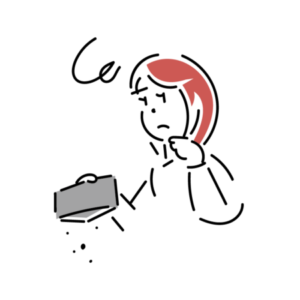 このように実際の支払額を大きく抑えることができる高額療養費制度ですが、「あとで払い戻される」という仕組みには問題があります。
このように実際の支払額を大きく抑えることができる高額療養費制度ですが、「あとで払い戻される」という仕組みには問題があります。
あとで戻ってくるとはいえ、いったん10~20万円を立て替えるのが難しい人も多いと思います。
そんな場合の対処法について解説します。
限度額適用認定証を利用する
あらかじめ申請をして「限度額適用認定証」を取得すれば、医療機関での窓口支払いが最初から上限額に抑えられます。
加入している健康保険(協会けんぽ、国保など)に申し込むことで、通常1〜2週間で交付されます。
高額療養費貸付制度
入院が急だった時など、限度額認定証が間に合わない場合に払い戻しされる分の一部を先に「貸付」として受け取れる制度です。
この貸付は無利子で、高額療養費の払い戻しと相殺されるため返済が不要です。
病院の相談窓口に事情を話す
病院によっては、支払いの分割や猶予に応じてくれるケースもあります。
「医療費の支払いが難しい」と感じたら、医療ソーシャルワーカーや患者相談窓口に早めに相談することが大切です。
高額療養費制度でカバーされない費用とは?
制度がカバーしてくれるのは「医療費」のみです。以下のような費用は含まれません。
- 差額ベッド代(個室利用など)
- 入院時の食事代(1食約460円)
- 先進医療の費用(例:陽子線治療など)
とはいえ、食事代は入院していなくてもある程度かかるものですし、他の費用は必ずしもかけなくてもいいものです。
本当に必要な保険は「自分の状況」次第
高額療養費制度の補償内容のを理解すると、民間の医療保険やがん保険の必要性に疑問を持つようになります。
しかし、「家計にかなりの負担になっているし、医療保険はすべて解約してしまおう!」と即決してしまうのは危険です。

保険の必要性は人それぞれです。収入や貯蓄の状況、家族構成、そして考え方によっても最適な選択は変わります。
ここでは、還暦世代が保険を見直す際に意識しておきたい判断のポイントを整理しておきましょいう。
貯蓄や収入で医療費をまかなえるか?
《ある程度の貯蓄がある人》
高額療養費制度の自己負担上限(月6万〜8万円程度)を貯金でカバーできるなら、保険の優先度は下がります。
たとえば、月1万円の保険料を払うよりその分を積み立てた方が使い道が限定されず柔軟に使えます。
《貯蓄が不安・収入が限られている人》
突然の医療費支出に備えて、最低限の医療保険(入院日額型など)を確保することも選択肢に入れるべきです。
じゅうぶんな貯蓄がない場合、急場しのぎで借金などに頼ることになり、返済や利子負担がさらに家計を圧迫することになります。
入院中の生活費や収入減の備えは必要か?
《年金生活者で収入変動がない人》
入院で働けなくなっても収入が変わらないため、収入補填目的の保険は不要な場合が多い。
また、会社員の場合も健康保険の「傷病手当金」である程度の収入の確保ができるので、必ずしも民間の医療保険が必要だとはいえません。
 《自営業・フリーランスなどで収入が不安定な人》
《自営業・フリーランスなどで収入が不安定な人》
入院中の収入減に備えて、「就業不能保障」や「所得補償型」の保険の検討が必要です。
自分が働けなくなると収入が途絶えてしまったり、極端に減ってしまう場合は、入院すること自体が深刻な問題になります。
精神的な安心や価値観も大切
 《心理的なことを重視する人》
《心理的なことを重視する人》
「安心をお金で買う」という言葉があります。
利用できる制度や現実的にかかる費用などを理解したうえで、保険に入っていることが安心につながるのであれば、心理的な安心をお金で買っているとも言えます。
《合理性を重視する人》
「無駄な出費を抑えて必要なことだけにお金を使いたい」
そう思う場合は、制度の内容や民間保険の補償内容を精査したうえで、保険を見直すべきです。
保険を減らしてその分のお金を貯蓄に回す方が合理的だといえます。

高額療養費制度、傷病手当金、労災保険、介護保険など、公的保障の内容を知っていれば過剰な不安は不要になります。
制度を知らずに「何となく不安だから」という理由だけで入る保険はコスパの悪い買い物だといえます。
とはいえ、「安心の基準」は人によって違うこともまた事実です。
まとめ
高額療養費制度の解説を中心に、還暦世代が民間保険を見直す際に必要なポイントについて考えてみました。
日本の公的医療保険には充実した補償が備わっていて、知れば知るほど無意味な民間保険に入っていることに気づくことが多いでしょう。

ただ忘れていけないのは、「保険を見直す=解約する」ではないということ。
貯蓄の状態や働き方によって準備すべき補償は変わりますし、また「安心」についての考えによって保険加入の意義も変わってきます。
自分自身の状態を正確に把握して、必要な保障だけを残してムダを省くことが大切です。
たとえば…
●医療医療保険の入院日額補償を1万円から5,000円に減らす。
●がん保険の診断一時金を重視して入院給付は削る。
●複数の特約が付いた総合保険を単品型に切り替える。
こうした調整でも、月数千円単位で支出を抑えることも可能です。

60代は、人生後半のマネープランを見直す重要なタイミングです。
公的制度の理解を深めて、保険の見直しをはじめ、貯蓄と投資のバランスを考えるなど、「自分の現状に合ったリスクへの備え」を見つけていきましょう。
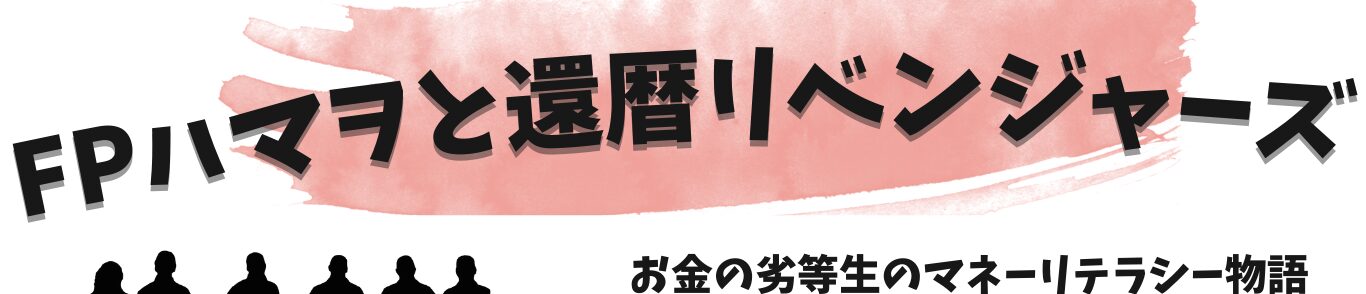



コメント