介護の現場で「ケアマネさん」と呼ばれる人をご存じだと思います。
このケアマネージャーの正式名称は「介護支援専門員」といいますが、ここでは馴染みのある「ケアマネ」でお話を進めましょう。
介護を受ける本人と家族、そして介護事業者をつなぐ司令塔のような存在といわれているケアマネですが・・・

実際に、どんな「立場」の人で、どんな「仕事」をしていて、どこから「報酬」を得ているのかなど、詳しく知っている人は意外と少ないものです。
この記事では、ケアマネの立場や仕事内容、報酬のしくみ、さらにケアマネの選び方についても、ケース別にわかりやすく解説します。
ケアマネージャーとは?どんな立場の人?
まず初めに理解しなければならないのは、ケアマネは「介護保険制度」の中のひとつの「役割」だということ。
そしてその役割は、介護を必要とする人の「介護サービス計画」を作成する専門職だということです。
この計画のことを「ケアプラン」といいます。
そして、このケアプランに沿って介護保険サービスをスムーズに利用できるようにする任務も負っています。

時には調整役として、そして相談役として、さらには応援団的な役割も努めます。
ちなみに、利用者本人と家族の暮らしを支える重要な存在であるこのケアマネですが、国家資格ではなく、「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格することで有資格者となります。
とはいえ、この資格を取得するには、医療や福祉系資格者(介護福祉士・看護師・社会福祉士など)として働いているか、相談援助業務(生活相談員・支援相談員など)の実務経験が規定を充たしている必要があります。

つまり、ケアマネは簡単に取れる資格ではなく、知識や経験の裏付けがあるものだということです。
ケアマネージャーの主な仕事内容
ではここで、ケアマネがどんな仕事をしているのかを見てみましょう。
その範囲の広さに驚くかもしれません。
ケアプラン(介護サービス計画)の作成
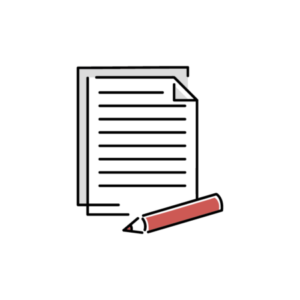 要介護認定の結果をもとに、本人や家族と相談しながら適切な介護サービスを組み合わせて計画を立てます。
要介護認定の結果をもとに、本人や家族と相談しながら適切な介護サービスを組み合わせて計画を立てます。
サービスの内容・利用回数・費用がきちんと伝わり、本人の希望に寄り添ったプランになっているかでケアマネの手腕が試されます。
サービス事業者との調整
デイサービスや訪問介護、福祉用具のレンタルや自宅の改装工事など、関係する複数の業者との連絡や調整を行います。
サービスの利用開始の手続きや搬入や工事日程の調整もケアマネの重要な仕事です。
本人・家族の相談対応
介護生活の悩み、介護費用、施設探しなど、本人や家族が直面する問題の相談相手にもなります。
また、ただの相談窓口ではなく問題解決にむけて行動し、状況の変化があれば敏感にプランの見直しに反映させます。
定期訪問・状況把握
原則月1回以上の訪問を行い、介護状況やサービスの利用状況、本人の体調の変化などを確認し、必要があればサービス内容の変更など、迅速に対応します。

介護を受ける本人だけでなく、家族などの状況を含めた介護の全体像を常に把握して、必要に応じた策を講じるという意味で、まさに介護の司令塔といえるでしょう。
ケアマネージャー、「所属」と「報酬」の仕組み
介護サービスにおいてなくてはならない存在であるケアマネですが、何となくフワッとした感じはしないでしょうか?
それは、ケアマネが「どこに所属」していて、「誰から報酬」をもらっているのか?
そんな疑問があるからかもしれません。
その点について整理してみましょう。
ケアマネはどこに所属している?
ケアマネには主に次の2タイプがあります。
《居宅介護支援事業所のケアマネ》
居宅介護支援事業所とは、要介護者が自宅で自立した生活を送るために、ケアプランの作成やサービス調整を行う事業所です。
在宅で暮らす要介護者のプラン作成・管理を担当し、サービスを提供する事業者と連携してより良い介護状態を目指します。
《施設系ケアマネ》
特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設に所属するケアマネです。
入居者のケアプランの作成から管理まで、担当するひとり一人の状態を常に把握し、対処します。
ケアマネの報酬のしくみ
利用者がケアマネに直接支払う料金はありません。ではケアマネはどこから報酬を得ているのでしょうか?
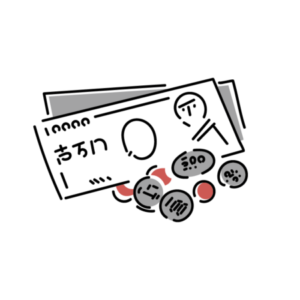 広い意味で言えば、ケアマネージャーの業務に対する報酬は介護保険から支払われます。
広い意味で言えば、ケアマネージャーの業務に対する報酬は介護保険から支払われます。
実際には、居宅介護支援事業所のケアマネの場合は「居宅介護支援費」として国から事業所へ支払われ、そこから報酬が渡されます。
施設系ケアマネの場合は、施設運営費の中から給与として支給されます。
ケアマネージャーを選ぶときのポイント
ケアマネはの資格は、医療や介護の分野の資格を持ち、現場で経験を積んだ人しか取得できません。
 しかもその仕事の範囲は多岐にわたり、任務を遂行するには多くの人と良い関係を築く必要もあります。
しかもその仕事の範囲は多岐にわたり、任務を遂行するには多くの人と良い関係を築く必要もあります。
そんな大変な仕事をこなしている方々ですから、どのケアマネさんを選んでも安心して任せられる・・・かといえばそんなこともないようです。
基本的に、ケアマネは介護サービスを利用する側が自由に選ぶことができます。

そこで、失敗しないケアマネ選びのふたつのポイントと、そもそも、どのタイミングで、どうやって選ぶのか?という点を整理しておきましょう。
ケアマネ選びのポイント
①話をじっくり聞いてくれるか
初対面での印象だけでも参考になる場合も多いです。
本人や家族の話を丁寧に聞いてくれるか?質問に対して理解できるまで答えてくれるか?希望や不安を積極的に聞き取ってくれるか?
など、ある程度の時間話をすれば感じ取れるものです。
②サービス事業者との調整力・対応の速さ
介護サービスの調整が遅かったり、連絡がとりにくいケアマネだと介護生活が不安定になります。フットワークの軽さ・説明のわかりやすさも大事なポイント。
どのタイミングで、どうやって選ぶのか?
状況によって選び方のタイミングや方法はいろいろなので、3つのケースごとに整理しました。
【ケース①】そろそろ考えたいとき
 今すぐに決める必要がなくても事前に情報が欲しい場合には、地域包括支援センターに相談することができます。
今すぐに決める必要がなくても事前に情報が欲しい場合には、地域包括支援センターに相談することができます。
もちろん要介護認定を受ける前でも大丈夫です。
そこで近隣の居宅介護支援事業所の情報やそこに所属しているケアマネについても調べることができるので、気になる事業所があれば、見学や事前の相談に訪問するのもいいでしょう。

緊急性がない時の方が冷静な判断ができる場合があるので、後で公開をしないためにも良いタイミングかもしれません。
【ケース②】要介護認定を受けたとき
要介護のレベルにもよりますが、認定が出た場合には現実的に話を進める必要があります。
在宅でサービスを受けるのか?デイサービスと組み合わせるのか?近い将来には施設入所も必要になるのか?など、専門家の意見を聞かなければなりません。
その場合は、市町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターに連絡します。
サービスを受ける事業所が決まれば、ほぼ自動的にそこに所属しているケアマネが担当ケアマネとなり、介護度や利用者の状態に応じてサービス内容を調整していきます。

居宅介護支援事業所と介護保険施設は違うものですが、同じ場所に併設する形で運営されているケースも多く、その場合、通常はひとつの施設として捉えられています。
【ケース③】急に介護が必要になったとき
 急な病気やケガをきっかけに介護が必要になる場合があります。
急な病気やケガをきっかけに介護が必要になる場合があります。
多くの場合は、病院を退院するタイミングで自宅に戻ってからの生活が困難になるケースで、急いで対応策を考えなければなりません。
家族が全面的に介護をできる場合は少なく、何かしらのサービスの必要性はででくるから。
このケースでは、入院している病院の医療ソーシャルワーカー(MSW)に相談するのが一般的です。

医療ソーシャルワーカーは医療機関で働いていて、患者本人とその家族の相談役となり、さまざまな問題の解決や手配を行う専門家です。
入院時から退院後の生活まで、患者の身体の状態や精神的な面、そして家庭環境や経済的状況などを総合的に把握して対応策の提案を行います
介護の専門家ではありませんが、退院直後の生活など緊急な対策についても、地域の事業所と連携し、受け入れの可否の確認を含めて対応してくれます。
ケアマネの変更もできる
事前によく調べたり実際に会って面談をした場合でも、担当になったケアマネに不満を持つこともあるでしょう。
仕事の進め方には様々な考えがありますし、人間同士の相性の良し悪しというのもあります。

もし「対応が悪い」とか「相性が悪い」と感じたときはケアマネを変更することも可能です。
本人には直接言いづらいでしょうから、地域包括支援センターや役所の介護保険担当窓口に相談するのがよいでしょう。
まとめ
介護を受ける本人と家族、そして医療機関や介護事業者などをつなぐ司令塔のような役割を負っているケアマネージャー。
とても重要な存在だというのはわかっていても、何となく実態が分かりづらいケアマネの仕事について整理しました。
 「仕事内容は?」「どこの所属しているの?」「誰から報酬をもらっているの?」
「仕事内容は?」「どこの所属しているの?」「誰から報酬をもらっているの?」
という素朴な疑問から、
介護に直面した時に必ず出てくる、
「どうやって選ぶの?」「どの段階で決めるの?」「誰に相談すればいい?」
という現実的なことまで、想定されるいくつかのケース別にまとめたので、大きなンあがれはつかめたのではないでしょうか?
とはいえ、実際にその場面が自分のことになると、さらに疑問や問題が出てくるのが普通です。
そんな時には、「地域包括支援センター」や「役所の介護保険担当窓口」に相談するのがよいでしょう。
そして、信頼できるケアマネ探しのためには、少し早い段階から情報収集を始めるのも有効な手段です。

いずれにしても、介護をめぐる環境を少しでも良いものにするためには、介護保険をはじめとした制度の全体像を把握して、関係する人たちそれぞれの役割を理解することが大切です。
<<関連記事➡いつか必ず直面する「介護」の要!公的介護保険の仕組みとキーパーソンをわかりやすく解説
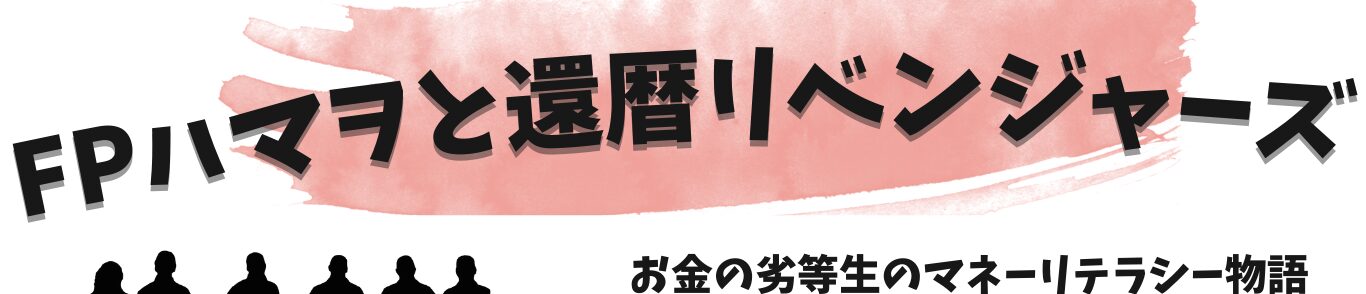


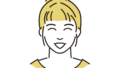
コメント