「最近、母親が何度も同じこと言う」「父親が財布を何度も失くすようになった」
そんな時、
「もう歳だから仕方ないのかな?」と思いながらも、「もしかしたら認知症かも・・」という不安な気持ちもあるのではないでしょうか。
この記事では、認知症かもしれない・・という不安を感じたときに相談すべき窓口や医療機関、認知症と介護保険との関係、利用できるサービスの内容などをわかりやすく解説します。
認知症かも?と思ったら、まずどこに相談する?
自分の親が認知症かもしれない・・と思ったとき、まずどうしたらいいのでしょうか?
当然自分では解決できませんから、誰かに相談しなければなりません。
思い浮かぶのは病院ですが・・
「病院に連れて行きたいけど嫌がるかな?」「病院の何科を受診したらいいのかな?」と戸惑うこともあるでしょう。
ここでは、最初の一歩として考えるべき3つのケースを考えてみましょう。
《ケース①》いきなり病院に連れて行くのが躊躇される場合は、
「地域包括支援センター」に相談するのがひとつの方法です。

地域包括支援センターは各市区町村に設置されている公的な相談窓口で、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるように、様々な相談や支援を行っています。
ケアマネージャーや保健師、社会福祉士が常駐していて、医療機関との連携や介護保険の手続きなど、今後どうすればいいかを案内してくれます。
もちろん、「もしかしたら認知症かも?」という程度の心配事についても気軽に相談ができます。
《ケース②》いきなり専門の病院に連れていくのに抵抗がある場合は、
まず、「かかりつけの病院」に相談するのがいいでしょう。
高齢者のほとんどはかかりつけの病院やクリニックがあり、定期的に受診して診察や検査、薬の処方などをしてもらっていると思います。

まず、馴染みのあるかかりつけ医に相談することで、簡単な認知機能検査が受けられる場合もあり、必要に応じて専門医療機関への紹介状も出してもらえます。
《ケース③》家族から見て、明らかに深刻な認知症の症状がある場合は、
 「認知症疾患医療センター」の受診を考えるべきでしょう。
「認知症疾患医療センター」の受診を考えるべきでしょう。
専門的な診断・支援体制が整っており、認知症の診断が必要な場合に受診する医療機関です。
全国に15か所ある「基幹型」と呼ばれるものをはじめ、規模などによって分類されていますが、「総合病院に併設」されているものや、「専門医のいるクリニック」などもあり、精神科・神経内科・脳神経外科などが中心です。
この3つのケースのどれも躊躇してしまう場合でも、一人で考え込んでしまうのはよくありません。信頼できる親戚や友人など、とにかく誰かに相談することで道が開ける場合もあります。

いずれにしても、認知症と診断された場合は、その程度に応じたケアが必要になります。
そこで関係してくるのが「介護保険制度」です。
公的介護保険制度を利用した介護サービスを受けるには、いくつかの手順を踏まなければなりません。
要介護認定と認知症の関係
認知症と診断された場合でも、自動的に介護保険が使えるわけではありません。
介護保険を使うには「要介護認定」を受ける必要があり、認知症を理由に介護サービスを受ける場合も例外ではありません。
では、要介護認定の流れを見てみましょう。
《要介護認定の流れ》
- 市区町村の窓口または地域包括支援センターに申請
- 訪問調査員による認定調査(認知機能もチェック)
- 主治医意見書の作成
- 介護認定審査会による判定 要支援1~要介護5の結果通知
<<介護保険の手続きについてもっと詳しく➡「いつか必ず直面する「介護」の要!公的介護保険の仕組みとキーパーソンをわかりやすく解説」
審査の際には、身体機能が理由の場合と同じで、認知症の症状により「日常生活にどの程度支援が必要か」が判断材料になります。
身体機能の要介護と認知症の要介護の違い
 認知症が理由の場合でも、要介護申請の流れや審査の基準は、身体機能が理由の場合と同じです。
認知症が理由の場合でも、要介護申請の流れや審査の基準は、身体機能が理由の場合と同じです。
しかし、受けられるサービスについては要介護度が同じでも内容に違いがあります。
例えば「要介護3」の場合・・
- 身体機能の低下(例:骨折、寝たきり)が理由の場合は、移動・入浴・排せつなどの身体介助が中心になります。
- 認知症による判断力の低下が理由の場合は、見守り・声かけ・徘徊対策などの活動支援が中心です。
認知症の場合は、身体介助よりも「安全確保」「生活リズムの維持」「孤立防止」が重視されます。
では具体的に、どんな場所で、どんなサービスが受けられるのでしょうか?
要介護認定されたら使える介護サービス
認知症を理由に要介護認定を受けたときに利用できる介護サービスの内容と、サービスを受けられる施設などをまとめました。
通所介護(デイサービス)
日中、送迎つきで施設に通い、食事・入浴・レクリエーション・機能訓練などを受けられます。
認知症対応型デイサービスでは、少人数で穏やかな雰囲気の中、認知症に理解のあるスタッフが対応してくれます。
小規模多機能型居宅介護
1つの施設で「通い」「泊まり」「訪問」を柔軟に組み合わせられる在宅介護サービスです。
顔なじみの職員が対応し、徘徊・夜間不安などにもきめ細かく対応できる点が、認知症の方には大きなメリットです。
訪問介護(ホームヘルプ)
掃除・買い物・調理などの生活援助や、排せつ・食事の介助を自宅で受けられます。
ただし、認知症の場合は対応できる事業所が限られてしまうのが難しい点です。
認知症グループホーム
軽度~中等度の認知症の方が、少人数で共同生活を送りながら介護職員の支援を受ける施設です。
家庭的な雰囲気の中で、見守り・生活支援・認知症ケアを受けられ、長期的な安心感があります。

認知症の介護は、身体機能低下の場合とは別の配慮が必要になります。要介護度による違いもあり、また同じタイプの施設でも対応できる場合とできない場合があります。
施設選びは、ケアマネージャーとよく相談をして慎重に行いましょう。
<<ケアマネージャーについて詳しく➡介護の司令塔!ケアマネージャーとは?役割・仕事内容・報酬のしくみをわかりやすく解説
そのほか、認知症の人を支える制度
高齢者見守りネットワーク:市区町村で実施しており、地域ぐるみで徘徊や安否確認を支援が受けられます。
成年後見制度:判断能力が低下した場合の財産管理や契約の支援が受けられます。
これらの制度については、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談すれば詳しく教えてもらえます。
まとめ
「自分の親が認知症かもしれない」と不安になったとき、「何から始めればいいのか分からない」と感じるのが普通です。
そこで頼るべきはやはり、公的介護保険制度です。

社会保険の制度はどれも仕組みが分かりづらく、手続きがめんどうな印象がありますが、行動し始めるとそれほど難しくないことに気がつくでしょう。
まずは地域包括支援センターやかかりつけ医に相談して要介護認定を受けることで、介護サービスを受けるための道が開けます。
還暦世代になると、親の介護が現実的になってきます。

「自分の親はまだ大丈夫」と思いたい気持ちもあり、特に、認知症の場合は判断が難しかったり、本人の気持ちを考えすぎてしまったりして行動を躊躇してしまいがちです。
認知症は投薬などの治療で症状を抑えられたり、進行を遅らせることができる場合もあります。
なるべく早い対応で医師の診断を受け必要な介護サービスを検討することが、本人にとっても家族にとっても大切です。
介護保険制度には、身体的理由による介護だけでなく認知症の人とその家族を支える仕組みが整っています。
「認知症かも」と思ったらひとりで抱え込まず、公的な制度を頼るべきなのです。
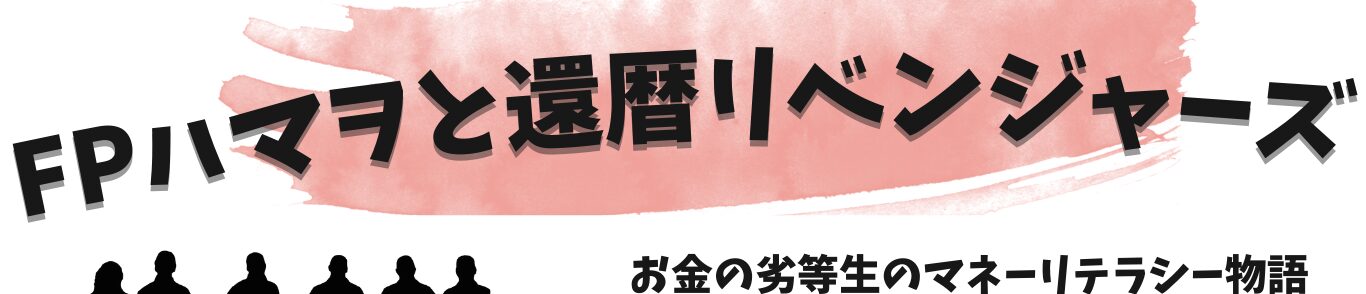
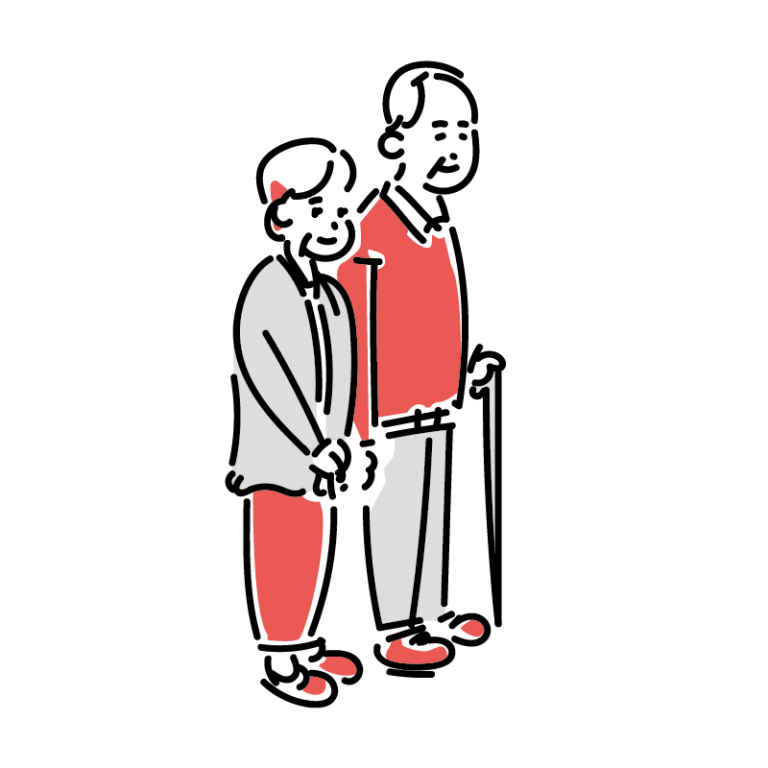
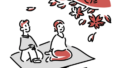

コメント