保証内容もよくわからないまま長い間加入し続けている生命保険。そのために支払い続けてきた保険料。
定期保険で満期を迎えるにせよ、終身保険でこれからも続くにせよ、還暦付近の年頃は保険見直しの時期でもあります。

子供も独立したし、万が一自分の身に何かあってもとんでもない事にはならないはず。でもまったく保証がないっていうのも不安だし・・
家族それぞれの状況が変われば必要な保証が変わるのは当然のことです。

うちは結婚が遅くて子供たちもまだ学生だから、充実した保証は必要。でも実は保険のこと良くわからなくて・・
テレビ、新聞、雑誌、そしてネット。日々目にするものの中に民間保険の情報は溢れています。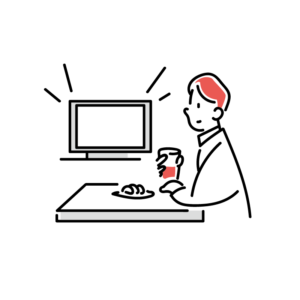
情報というより広告と言った方が正確かも知れませんが。
生命保険、がん保険、自動車保険・・、保険会社がメディアにとって大きな広告主であることは間違いありません。
そんな大人の事情とも言える性質上、大手のメディアでは民間保険に対するネガティブな情報はほとんど目にすることがありません。
その論じられない話題の中でも、保険を考える際に絶対に知っておくべきことが「社会保険」いわゆる公的保険の制度です。
ということで、今回のテーマは、

意外と知らない、世界でも稀な充実した保証。日本の社会保険制度について。
病気や怪我、そして万が一亡くなった場合に、健康保険や年金制度から加入者本人や家族が受けられるさまざまな保障。
その社会保障制度の内容を知らずして民間の保険を選ぶことは決して賢明とは言えません。
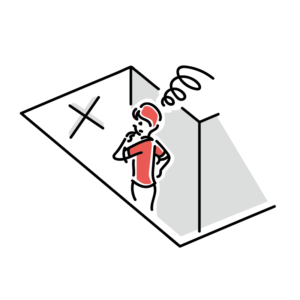 人生100年といわれる今、私たち還暦世代にとっても人生はまだまだ続くのです。
人生100年といわれる今、私たち還暦世代にとっても人生はまだまだ続くのです。
社会の先行きが見えないなか、これからのリスク管理には慎重に取り組まなければなりません。
ところがこの社会保障の制度はものすごく分かりづらい状態になっていて「迷宮」といってもいいほど。
細かいところまで完全に理解しようとするのは無理な話でしょう。
そこで今回は、還暦世代がこれからの生活設計を考えるうえで大変重要なこの社会保険について、まずは超基本的な構造を確認しておきたいと思いますます。
日本の社会保険の超基本
社会保険とは、年齢などの条件に当てはまる場合、必ず入らなければいけない、いわゆる強制加入の公的な保険制度です。
保険の種類は次の5つ。
年金制度、健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険です。
今回はこの中で、民間の生命保険や医療保険を考える際、特に知っていなければならない「年金制度」と「健康保険」について見ていきましょう。
年金制度
20歳から60歳未満の全ての国民は「国民年金」に加入しなければなりません。
その40年の期間に「年金保険料」を納め、そして基本的には65歳から「老齢年金」が受給できる。
そしてそれは一生涯・・つまり死ぬまで続きます。
このように、基本はいたってシンプルなのですが、実際にはとても複雑な構造になっています。

その複雑な構造が生み出すもっとも深刻な問題が「年金の格差」なのです。
どうして年金に格差が生まれるのか?
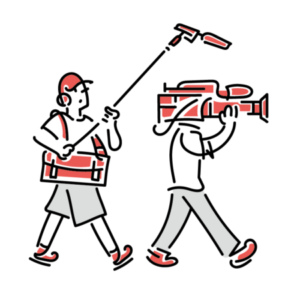 報道番組などでしばしば目にする「困窮した高齢者の生活」その原因のひとつは「少ない年金額」です。
報道番組などでしばしば目にする「困窮した高齢者の生活」その原因のひとつは「少ない年金額」です。
その一方で、現役世代が働いて手にする給料よりも大きな額の年金を受け取っている高齢者もいる。
厚生労働省の資料によると、国民年金受給者と厚生年金受給者の平均年金額は2.5倍以上の差があります。

年金は強制加入でしょ。全員が加入して保険料を納めるものなのに、どうして受け取る年金額にそんなに大きな差が出るのかな?

その疑問を解明するには、「国民年金」と「厚生年金」の違いを理解しなければなりません。
国民年金には20歳から60歳未満の全ての国民が加入します。
といっても、実際に「国民年金保険料」という形で納めているのは自営業やフリーランス、そしてその配偶者など、会社に雇われていない人が主です。
また、雇われている場合でも、雇用形態や働く時間などの関係で国民年金加入の人もいます。
厚生年金には会社員や公務員が加入し、保険料は給与から天引きされます。
その保険料は収入によって変動し、高収入になれば納める保険料も高くなり、それに応じて将来受け取れる年金額も多くなります。

勘違いしがちなことですが、「厚生年金」に加入している人も、厚生年金の保険料を納めることで、同時に国民年金にも加入している扱いになります。
さらに、厚生年金加入で働いている夫に扶養されている専業主婦も、保険料の納付無しで国民年金に加入していることになります。
つまり、夫の給与から引かれている「厚生年金保険料」には、「本人の国民年金保険料」と「本人の厚生年金保険料」、専業主婦の妻がいれば「妻の国民年金保険料」がすべて含まれているということです。

その「負担なしで納めたことになっている妻の保険料」って、なんか納得できないけど・・
そう感じるのも当然ですが、これは長い間に幾度となく行われてきた年金制度の改定の中で、「サラリーマンの数を増やしたい」という国の方針によって生まれた、いわゆる会社員優遇のためのものなのです。
そして、この厚生年金保険料は「労使折半」といって、本人と会社で2分の1ずつ負担しています。つまり、実際には給与から天引きされている金額の2倍を保険料として納めています。
その結果として、将来受け取る年金受給額も厚生年金の方が多くなるというわけです。

さらに、この「給与から天引きされる」という点が、年金受給額の差を生むもう一つの原因でもあります。
有無も言わさず保険料を支払うとなると、良くも悪くも保険料を納めないという選択肢はありません。
もちろん、強制加入である国民年金は当然その保険料の納付も義務となっています。ただ、義務であれば全員が必ず納めるか?・・というと、現実はそんなことはありません。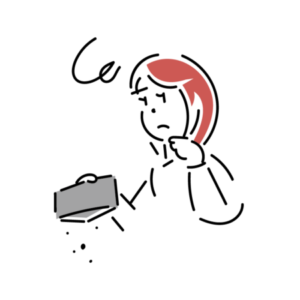
今はお金が無いからと先延ばしして、その結果、払えないというケースも多い。
更に言えば、未納でも、税金のように財産の差し押さえなどの措置が取られないために、意図的に払わないという人もでてきます。

無理して保険料を納めても、結局自分たちが受給年齢になる頃には年金制度は破綻して一円ももらえないかも・・
という感じで開き直って払う気さえない人もいます。
実際に年金破綻説はずっと前からまことしやかに語られていますから、そんなふうに考えてしまうのも無理はありません。
ただ、そもそも年金は保険と同じ仕組みで運営されているので、理論的には破綻はありえないのです。
しかし、この年金破綻の噂も手伝ってか、国民年金の保険料の未納者はけっこう多い。

保険料を満額納めていても受給額は決して多くない上に未納期間のある人が多い。この現実が年金受給額の大きな差を生んでいるのです。
そしてこの「国民年金」と「厚生年金」の違いは65歳から受け取る老齢年金の金額だけでなく、それ以外の年金の受給条件にかかわりがあるのです。
知っていますか?「老齢」以外の2つの年金
意外と知られていないのが、歳をとってから受け取る老齢年金以外にも状況に応じて受け取れるふたつの年金。
「遺族年金」と「障害年金」です。
《遺族年金》
国民年金や厚生年金の加入者が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた配偶者や子どもなどが受け取れる年金。(遺族の年齢や人数によって受給額が変わる)
《障害年金》
障害認定を受けた場合に加入者本人が受けられる。(障害の程度によって受給額が変わる)
このふたつにも、国民年金から出る「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」、そして厚生年金から出る「遺族厚生年金」「障害厚生年金」があります。

「遺族」と「障害」このふたつの年金について、国民年金と厚生年金の違いをみていきましょう。
遺族年金
子供がいないともらえない遺族基礎年金
《遺族基礎年金》
遺族基礎年金は国民年金から支給される年金です。
受給対象となるのは、「亡くなった人によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』」となっています。
ここでいう「子」とは、高校卒業までの年齢を意味します。
逆に言えば、高校生までの子供がいなければもらえない。また、受給開始時点では子供がいても、その子が高校を卒業する年齢までで受給はストップするということです。

たとえば、高校生までの子供がいるお父さんが亡くなった場合は奥さんがもらえる。もし奥さんがいない・・つまり父子家庭なら子供が直接もらうということです。
遺族基礎年金の年金額は一律ですが、子どもの人数によって金額が変わります。
およその年金額(令和6年の年額)は、約81万円+子供一人当たり約23万円(3人目の子からは約8万円)です。
そして遺族基礎年金を受給するためのもうひとつの条件が、保険料の納付に関することです。
死亡日の前日までの保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)の合計が、国民年金加入期間の3分の2以上必要です。
ただし、その条件を満たさなくても、次の条件すべてに当てはまれば受給することができます。
①死亡日において、65歳未満である。
②死亡日の前日時点でその月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない。

つまり、納付期間が短くても、直近の1年間ちゃんと納めていれば、それが評価されて年金がもらえるというわけです。
このように国民年金からもらえる遺族基礎年金は、小さい子供がいるかどうかが受給の分かれ道となります。
子どもがいなくてももらえる遺族厚生年金
《遺族厚生年金》
遺族厚生年金は厚生年金から支給される年金です。
厚生年金に加入していた人が亡くなった際に、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取れる年金です。
二階建てといわれる年金制度の性質上、遺族厚生年金が受給できる人は基本的に遺族基礎年金ももらえます。

そして、国民年金からもらえる遺族基礎年金との大きな違いは、子どもがいてもいなくても関係ない、ということです。
亡くなった夫に妻がいれば、子供がいるいないに関わらず受給件があります。
妻がいない、つまり父子家庭だった場合は子供が受給者になりますが、受給期間は高校卒業の年齢までとなります。
ただし、妻が30歳未満で子供がいない場合は、5年間の期限付きの受給となります。

妻が20代で子供がいなければ、5年間の準備期間を経て自立してください、というような意味なのでしょう。
このように、遺族年金に関しても国民年金より厚生年金のほうが有利な点が多いといえます。
障害年金
障害年金は、病気やけがで生活に支障が出たり、できる仕事が制限されてしまう場合にもらえます。
年齢要件は基本的にありません。

年齢要件が無いということは、まだ年金に加入していない20歳前や60歳から65歳の人も対象になるということです。
障害年金についても、国民年金から支給される「障害基礎年金」と厚生年金からの「障害厚生年金」があります。
どちらの年金がもらえるか?というと、それはその病気になったり怪我をした時点で、どちらの年金に加入していたかによって決まります。

怪我の場合はわかるけど、病気って、いつなったのか良くわからないことの方が多いと思うけど・・?

この場合は「初診日」がその日になります。その病気や怪我で初めて医師の診療を受けたときということですね。
ではまず、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の共通点をまとめます。
《保険料納付要件》
障害基礎年金・厚生年金とも、受給するためには次の保険料納付要件のどちらかを満たす必要があります。
①初診日のある月の前々月までに、加入期間の3分の2以上の期間に保険料が納付(免除を含む)されていること。
②初診日において65歳未満で、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

この点は遺族年金と同じで、納付期間が短くても直近の1年間ちゃんと納めていれば、それが評価されて年金がもらえるというわけです。
《受給できる金額》(令和6年の年額)
国民年金加入で受給できる障害基礎年金の金額は障害の等級によって変わります。
1級・・1,020,000円 + 子の加算額
2級・・816,000円 + 子の加算額
※子の加算額は1人につき234,800円(3人目以降は78,300円)
このように1級の金額は2級の1.25倍になっています。
では「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の違う点をまとめます。
厚生年金加入の場合は、この障害基礎年金の金額に障害厚生年金が上乗せされることになります。
《障害厚生年金で上乗せされる金額》
1級・・報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額
2級・・報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額

報酬比例の年金額って、平均の給与とか年金の加入月数で決まるわけでしょ。もしも若い時に障害になったら、すごく少ない金額になると思うけど・・?

そうならないように、厚生年金期間が300ヵ月(25年)未満の場合は、300ヵ月とみなして計算するのです。
配偶者の加給年金というのは家族手当のようなもので、配偶者が65歳になるまで、年額23万円程度が受給できます。
上乗せ分があることで、この障害年金に関しても厚生年金加入者のほうが有利といえます。

さらに違う点がもうひとつ。それは、障害厚生年金には障害基礎年金にはない「障害等級3級」があることと、「障害手当金(一時金)制度」があることです。
これは、2級より障害の程度が低い場合に受給できる「3級の障害厚生年金」や、障害年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときの「障害手当金(一時金)」を受け取ることができる制度です。
障害基礎年金には「3級」はないので、障害厚生年金で受給できる金額は、報酬比例の年金額のみとなり、配偶者の加給年金額がないこと以外は2級と同じです。
さらに、60万円程度の最低保証額があり、障害基礎年金が受給できない部分をだいぶ補うことができます。
ただし、3級の障害厚生年金を受給した場合には、それ以降の国民年金保険料の免除はありません。
健康保険
誰もが良く知るお馴染みの制度です。
病気や怪我で病院に行くと、健康保険証を出すように言われます。

当たり前のようにそう言われるのは、誰もがこの健康保険に加入しているという前提があるからです。これを「国民皆保険」といいます。
そしてこの健康保険証を提示することで、窓口で支払うお金が「自己負担分」だけで済みます。
《自己負担の割合》
自己負担の割合は基本的に年齢で段階的に別れています。
未就学児は2割
6歳~69歳までは3割
70歳~74歳までは2割
75歳以上は1割※70歳以上に関しては収入が高い場合は負担割合が変わることがあります。
健康保険の3つの制度
健康保険は、大きく3種類に分かれます。
「健康保険」、「国民健康保険」、「後期高齢者医療制度」です。

「健康保険」と「国民健康保険」・・とてもよく似た名前ですごくややこしいですが、仕方ありません。違いをしっかり確認しましょう。
《健康保険》
会社員や公務員が加入する制度で、それがさらに3種類に分類されます。
「組合健保」・・大企業などが独自に運営し、そこで働く人が加入。
「協会けんぽ」・・中小企業などで働く人が加入。
「共済組合」・・公務員や私立学校の職員が加入。
この健康保険の特徴は「扶養」が認められているということです。

つまり、健康保険に加入している人に扶養家族(妻や子供など)がいる場合、追加の保険料なしで、その家族も同じ保険が適用されるということです。
《国民健康保険》
主に自営業者やフリーランス、農業や漁業に従事する人が加入します。その他、雇用形態などの関係で職場の健康保険に加入できない人もこの制度に加入します。
運営は都道府県と市区町村が行い、保険料はそれぞれの自治体が決定します。
その保険料の算定方法はかなり複雑なので、正確な数字は窓口に問い合わせなければ分かりません。
この国民健康保険の特徴は「扶養」が認められていないということです。

たとえば、国民健康保険に加入している自営業者の場合、配偶者や子供はそれぞれに国民健康保険に加入しなければならないということになります。保険料は世帯ごとに算出され、世帯主が一括して納めます。
また、国民健康保険の中には、同業種、同職種で組織される国保組合があります。医師、歯科医師、看護師、薬剤師、建設業など職業は限られますが、該当する場合はこちらの方がメリットがあるようです。
《後期高齢者医療制度》
75歳以上のすべての国民はこの制度に加入します。
健康保険に入っている人も国民健康保険の加入者も、75歳になった時点で後期高齢者医療制度の被保険者となります。
医療費の自己負担割合は1割(現役並み所得者は3割)で、保険料は都道府県が計算し、徴収は市区町村が行います。
3割負担の他にもある!健康保険の強力な保証
この、「医療費の自己負担3割」というのがもっとも身近で、ほとんどの人が日常的に触れている健康保険の保証です。
しかし健康保険加入のメリットはそれだけではありません。
ここで、「傷病手当金」と「高額療養費制度」について確認しておきましょう。
傷病手当金
傷病手当金は、会社などに雇用されて働いている人が、病気や怪我で働けなくなった時に支給されます。

通常、会社を休むとまずは有給休暇を消化する形で給与に影響が出ないようにしますが、有給の残日数がない場合は欠勤控除となり給与が減ってしまいます。そうならないための保証が傷病手当金です。
とはいえ、2〜3日休んだからといって適応されるわけではなく、一定の規定が設けられています。
《傷病手当金の規定》
会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降から支給される決まりになっています。
支給される期間は最長で1年6カ月。
支給される金額は休んだ日数×1日当たりの金額です。1日当たりの金額は、直近12カ月間の、1ヶ月あたりの平均給与の3分の2で計算します。

つまり月給の約3分の2が支給されるわけですが、会社から報酬を受け取っていた場合、その金額は支給額から差し引かれます。
おおまかな決まりごとはこのようになっていますが、直近12カ月の間に勤務先が変わっていたり雇用形態が変わっていた場合は計算方法が少し変わります。
また、障害年金や障害手当金を受けている場合、労災保険から給付を受けている場合などは条件が異なります。

忘れてはいけない重要なポイントは、この傷病手当金という保証は、国民健康保険にはないということです。
これは、ケガや病気で「会社を休んだために給料が減ってしまうことに対する保証」です。
自営業者やフリーランスには「会社を休む」ということが当てはまらないと考えられているからです。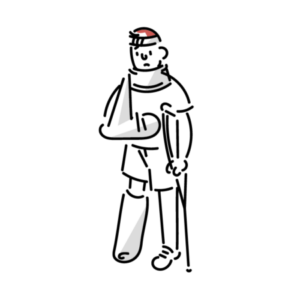
対策としては個人事業主向けの休業補償保険などを検討するしかありませんが、ある程度のコストを覚悟しなければなりません。
高額療養費制度
入院や手術などで多額な医療費がかかったとしても、限度額以上の医療費を負担しなくて済む制度です。
医療保険でほとんどの人がメリットを感じるのが医療費の3割負担です。

でも大きな病気で入院とか手術をしたら3割負担といってもかなりの金額になるよなぁ・・
もしも医療費が100万円かかったら3割負担でも30万円。これは大きな負担ですし、実際に払えないというケースも多くなるでしょう。
そんな時に利用できるのが、この「高額療養費制度」です。
《高額療養費制度》
これは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
限度額は所得によって区分されていていますが、標準的な所得であれば5万円~8万円程度。さらに治療が長期にわたった場合に備えて、4カ月目からはさらに自己負担額が低く抑えられています。

かんたんにいうと、「一カ月あたりの自己負担額の上限が決まっていて、それ以上は支払わなくていい」というものです。

後で戻ってくるといっても、いったん払うとなると、そんなお金用意できるかどうか・・
後から払い戻されるとはいえ、とりあえず支払わなければならないとなると、それは大きな負担です。
その場合は「限度額適用認定証」を提出することで、医療機関窓口での1か月のお支払いが最初から自己負担限度額までとなります。
この制度は、所得が極端に低い場合などは、ほとんど自己負担なく安心して医療が受けられる仕組みになっています。外国ではよく起きている「医療費で破産」「お金がなく医療が受けられない」といったことがないようにつくられた世界でもまれな制度といえます。
知らないことが生みだす2つの悲劇
日本の社会保障の柱ともいえる2つの制度、「年金制度」と「健康保険」について超基本的な構造をまとめてみました。
思っていたより守備範囲が広く、こんな場合にもピンチを救ってもらえるのか・・と驚いたかもしれませんが、この驚きこそがチャンスといえます。
知らないということが大きな損失につながるからです。

年金も健康保険も、ほとんどの保証は自分から申請しなければなりません。年金事務所が、病院が、職場が、役所が・・、勝手に手続きをしてくれて自然にお金がもらえる・・なんていうことはほとんど無いと言っていいでしょう。
つまり、知っていなければほとんど意味がないのです。
利用できる制度や受けられる保証は、まさにケースバイケースです。年齢、家族構成、加入している制度、保険料の納付状況・・それぞれの人のその時々の状況によって大きく異なります。
だからこそ自分で行動する必要があるのです。
ステップ①どんな保証があるのかを知る。
ステップ②自分の状況がどのケースに該当するのかを調べる。
ステップ③必要に応じて申請の手続きをする。
とてもシンプルな手順ですが、ステップ①の「知る」がなければ何も始まりません。本来、当然の権利として受けられるはずの保証が、「知らない」ことでまったく受けられないという悲劇を生みます。

そして「知らない」ということが原因で起きるもうひとつの悲劇が、「間違った保険選び」なのです。
そもそも民間の保険というのは、私たちがほぼ強制的に加入させられている公的な社会保険を補完するものとして存在しているもの。
●病気やケガで仕事ができない。
●入院や手術で大きなお金がかかる。
●重い障害を負って一生涯生活に支障が出る。
●一家の大黒柱が突然亡くなって残された家族が路頭に迷う。
誰にでも起きる可能性があるこんな事態に備えて「ある程度の保証」を用意しているのが年金や健康保険などの公的な社会保険制度です。
そしてその「ある程度の保証」だけでは足りないという場合に必要になるのが民間の保険なのです。

つまり、社会保険の保証内容を知らずに民間保険で必要な保証を考えることは本来は無理なはずなのです。ところが実際は、そんな状態のままほとんどの人が保険に加入しています。そしてその結果、不必要な保険料を長期間にわたって払い続けていることも多いのです。
その理由には、メディアにあふれている不安を煽る保険会社の広告や保険営業マンの巧みなトーク。公的保証の内容を周知しきれていない行政の努力不足などがあるかもしれません。
しかし一番の理由は私たちの意識に他ならないのでは無いでしょうか。
特に私たち還暦世代は、長い期間社会人として生活し、仕事でも私生活でもいろいろなことを経験してきました。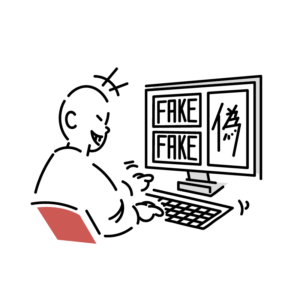
⚫︎社会の仕組みやビジネスの裏側。
⚫︎世の中にあふれる様々な仕組みや仕掛け。
⚫︎会社員が負っている職務の数々。
そういったものにうすうす感づいているはずです。
⚫︎テレビのCMに不安を煽られてばかりではいけない。
⚫︎メディアにはスポンサーとの関係で隠さなければならない真実もある。
⚫︎どんないい感じの人でも、保険営業のセールストークを鵜吞みにしてはいけない。

それを踏まえたうえで正しい選択をするためには、思考停止にならずに自分の頭で考え、積極的に情報を取りに行くことが必要なのです。黙っていても誰かがいちばんよい方法を教えてくれるということは絶対に起こらないのです。
家族や仕事など、自分を取り巻く環境が大きく変化する還暦付近の年頃は保険見直しの時期でもあります。
環境が変われば必要な保証が変わるのは当然のこと。

今までの保険選びは失敗だった・・。
これまでにどんなに無駄な保険料を払ってきたことか・・。
公的保険の保証を正しく知ることで、こんな後悔の念が沸き起こるかもしれません。
しかしそれは過去のこと。

人生100年時代。還暦の先はまだまだ続くのです。保険のことに限らず、失敗や後悔に力を落とさずに未来のために積極的に進んでいきましょう!
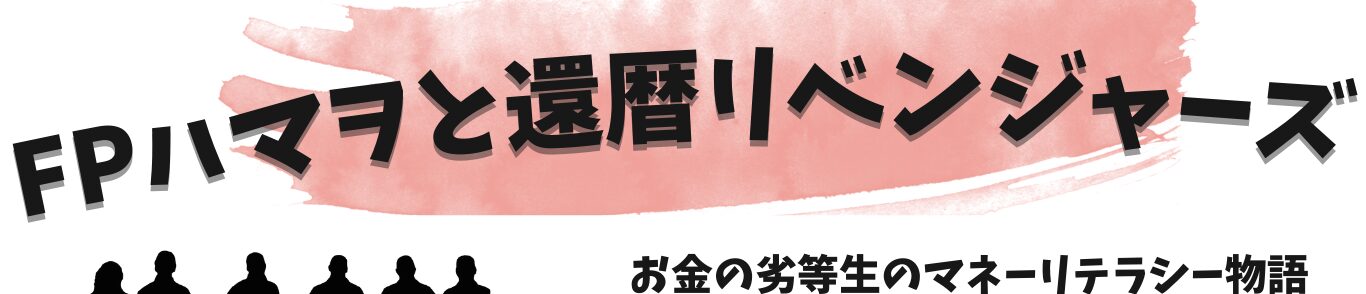

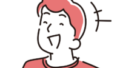

コメント